2025年7月7日
書類送検とは?前後の流れや前科・前歴がつくのか解説
ある日突然、警察から電話がかかってきて、「〇〇の件で話を聞きたいので、警察署まで来てください」と言われたら、誰でも冷静ではいられないでしょう。心臓が凍りつくような思いがし、これから自分の人生はどうなってしまうのかと、深い不安に襲われるはずです。
警察での取り調べが終わった後、「事件を検察庁に書類送検します」と告げられることがあります。逮捕されていないことから、「大事にはならなかった」と安堵する方もいるかもしれません。しかし、「書類送検」という言葉の意味を正しく理解している方は多くないのが実情です。
この記事では、法律に精通した専門家の視点から、「書類送検」とは具体的にどのような手続きなのか、その後の流れや、多くの方が心配される前科・前歴との関係について、分かりやすく解説します。もしあなたが今、警察から連絡を受け、先の見えない不安の中にいるのであれば、この記事から正しい知識を得て、次の一歩を踏み出すための助けとなることを願っています。

1. 書類送検とは
まず、「書類送検」という言葉の正確な意味からご説明します。この手続きは、刑事事件の捜査における重要な段階の一つであり、その後の展開を左右する起点となります。
ニュースなどで耳にする「書類送検」とは、警察が捜査した事件の記録を、検察官に引き継ぐ手続きのことです。刑事事件の捜査は、原則として警察が第一次的に行いますが、被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)を起訴するかどうか(裁判にかけるかどうか)を最終的に決定する権限は、検察官にあります。
そのため、警察は捜査を終えた事件を、原則としてすべて検察官に送らなければなりません。これを「全件送致主義」といい、法律で定められたルールです。
刑事訴訟法 第百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
この「送致」には、被疑者の身柄を拘束した状態で行う「身柄送検」と、身柄を拘束しない「在宅」のまま事件の書類や証拠物だけを送る「書類送検」の2種類があります。
つまり、書類送検とは、被疑者が逮捕されていない在宅事件において、警察から検察へ捜査ファイルが引き継がれることを指すのです。警察が逮捕に踏み切らないのは、被疑者に「逃亡や証拠の隠滅をするおそれ」が低いと判断した場合です。日常生活を送りながら警察の呼び出しに応じて取り調べを受けることになるため、身体的な拘束はありませんが、捜査が続いているという事実に変わりはないのです。
1-1. 書類送検される割合
「逮捕されなかった」という事実は、ひとつの安心材料かもしれません。しかし、書類送検がどれくらいの割合で行われているかを知ることで、ご自身の状況をより客観的に捉えることができます。
法務省が発行する「令和6年版犯罪白書」によると、令和5年中に検察庁で処理された事件のうち、過失運転致死傷罪と道路交通法違反を除いた刑法犯の事件では、約65.2%が書類送検(身柄不拘束)の形で処理されています。
この数字が示すのは、逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」が、決して例外的なケースではなく、むしろ半数以上を占める標準的な手続きであるという事実です。多くの方が、逮捕という最も厳しい措置を免れたことで、「もう大丈夫だろう」と楽観的に考えてしまう傾向があります。しかし、この高い割合は、事態の深刻さを決して軽減させるものではありません。書類送検は、あくまで検察官による本格的な捜査と処分の判断が「これから始まる」という合図なのです。この段階で適切な対応を取るかどうかが、その後の人生を大きく左右する可能性があります。
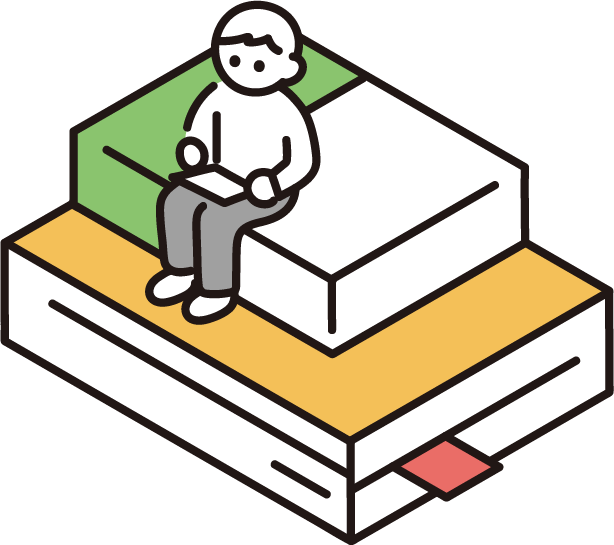
1-2. 書類送検の起訴率と不起訴率
書類送検された後、最も気になるのは「起訴されるのか、それとも不起訴になるのか」という点でしょう。この割合を知ることは、ご自身の置かれた状況のリスクを正確に理解する上で非常に重要です。
同じく「令和6年版犯罪白書」の統計によれば、令和5年において書類送検を含む検察庁で処理された事件の起訴率は、犯罪の種類によって異なります。
- 刑法犯の起訴率:36.9%
- 特別法犯の起訴率:45.4%
「刑法犯」とは、刑法に定められた犯罪のことで、窃盗、暴行、傷害、詐欺などがこれにあたります。一方、「特別法犯」とは、刑法以外の特別な法律で定められた犯罪で、例えば薬物関連の法律違反や、愛媛県迷惑行為防止条例のような地方自治体の条例違反などが含まれます。
このデータが示すのは、刑法犯の場合で約3件に1件、特別法犯に至っては約2件に1件が起訴されているという厳しい現実です。つまり、書類送検された事件のうち、不起訴となるのは刑法犯で63.1%、特別法犯で54.6%に留まります。
「起訴」とは、検察官が裁判所に対して正式な裁判を求める手続きのことで、これが行われると刑事裁判が開かれます。「不起訴」は、裁判を開かずに事件を終了させる処分です。逮捕されていないからといって、起訴される可能性が低いわけでは決してありません。むしろ、相当な確率で刑事裁判へと進むリスクが存在することを、この公式な統計データは明確に示しています。だからこそ、この段階で専門家である弁護士に相談し、不起訴処分を目指すための活動を始めることが極めて重要になるのです。

2. 書類送検と間違いやすい言葉の違い
刑事手続きには、一般の方には馴染みのない専門用語が多く登場します。特に似たような響きの言葉は、混乱や不安を増大させる原因にもなりかねません。ここでは、「書類送検」と混同されがちな言葉との違いを明確に解説し、ご自身の状況を正しく理解するための一助とします。
2-1. 書類送検と逮捕の違い
最も大きな違いは、身体拘束の有無です。
- 逮捕(たいほ)逮捕とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逃亡や証拠隠滅のおそれ」がある場合に、裁判官が発する令状に基づいて行われる強制的な身体拘束です。逮捕されると、警察署の留置施設などで身柄を拘束され、警察段階で最大48時間、検察段階で最大24時間という厳格な時間制限のもとで取り調べが進められます。
- 書類送検(しょるいそうけん)書類送検は、前述の通り、身体拘束を伴わない手続きです。被疑者は自宅で生活しながら、必要に応じて警察や検察から呼び出しを受け、取り調べに応じます。これを「在宅事件」と呼びます。時間的な制約も逮捕されている事件(身柄事件)ほど厳しくなく、捜査が長期化することもあります。
つまり、逮捕は「身柄」を拘束する強制処分であるのに対し、書類送検は「書類」だけを検察に送る手続きであり、両者の間には自由が制限される度合いに天と地ほどの差があります。
2-2. 書類送検と微罪処分の違い
次に、書類送検と微罪処分の違いです。これは、事件が検察官に送られるか否かという点で、決定的に異なります。
- 書類送検(しょるいそうけん)警察での捜査を終えた事件が、検察官に送られる手続きです。その後の起訴・不起訴の判断は、すべて検察官に委ねられます。
- 微罪処分(びざいしょぶん)犯罪事実が極めて軽微であるなどの理由から、検察官に送致せず、警察限りで事件を終了させる処分のことです。これは、刑事訴訟法が定める「全件送致主義」の例外として認められています。根拠となる条文は以下の通りです。刑事訴訟法 第百四十六条 ただし書…但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。犯罪捜査規範 第百九十八条(微罪処分ができる場合)捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
微罪処分となれば、警察からの厳重注意などで手続きは完了し、前科がつくことはありません。一方、書類送検は、事件が次のステージ(検察)に進んだことを意味し、起訴される可能性が残るという点で、その後の展開が全く異なります。
2-3. 書類送検と送検の違い
この二つの言葉の関係は、包括的な言葉と、その具体的な一種類という関係にあります。
- 送検(そうけん)「送検」は、警察が捜査した事件を検察官に送る行為全般を指す広い言葉です。ニュースなどで使われる一般的な用語です。
- 書類送検(しょるいそうけん)「書類送検」は、その「送検」の具体的な一形態です。特に、被疑者の身柄を拘束せず(在宅のまま)、事件の書類や証拠物だけを送る場合を指します。
もう一つの送検の形態として、逮捕した被疑者の身柄ごと検察官に送る「身柄送検(みがらそうけん)」があります。つまり、「送検」という大きな枠の中に、「書類送検」と「身柄送検」という二つの方法が存在すると理解すると分かりやすいでしょう。
2-3-1. 書類送検と書類送致の違い
結論から言うと、この二つの言葉は実質的に同じ意味です。
- 送致(そうち)「送致」は、刑事訴訟法などの法律で使われている正式な法律用語です。先に引用した刑事訴訟法第246条でも「送致しなければならない」と規定されています。
- 送検(そうけん)「送検」は、「検察官に送る」を略した言葉で、主に報道機関などが使う一般的な通称・マスコミ用語です。
したがって、「書類送検された」と「書類送致された」は、指し示す事態に何の違いもありません。法律の専門家は「送致」を、メディアは「送検」を使う傾向がある、という程度の違いです。

3. 書類送検だけでは前科はつかない
事件の当事者にとって、最も重くのしかかる懸念の一つが「前科がつくのではないか」という不安でしょう。この点について、正確な知識を持つことは、過度な不安を和らげ、冷静な対応をとるために不可欠です。結論として、書類送検されたという事実だけでは、前科はつきません。
3-1. 裁判で有罪になると前科がつく
「前科」とは、法律上の明確な定義はありませんが、一般的に「刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定した経歴」を指します。罰金刑、禁錮刑、懲役刑など、刑の種類を問わず、有罪が確定すれば前科となります。
刑事手続きの流れに沿って考えると、前科がつくまでのプロセスは以下のようになります。
書類送検 → 検察官による起訴 → 刑事裁判 → 有罪判決の確定 → 前科がつく
この流れから明らかなように、書類送検は、検察官が起訴・不起訴を判断するための入り口に過ぎません。この段階ではまだ裁判は開かれておらず、有罪かどうかの判断も下されていません。したがって、書類送検された時点では、前科がつくことは絶対にありません。不起訴処分となれば、裁判は開かれないため、もちろん前科がつくこともなく事件は終了します。
3-2. 書類送検されると前歴は残る
一方で、「前歴」という記録は残ります。この「前科」と「前歴」の違いを理解しておくことが重要です。
「前歴」とは、「犯罪の被疑者として、警察や検察などの捜査機関による捜査の対象になった経歴」を指します。捜査の対象となった時点で記録されるため、最終的に不起訴になった場合や、無罪判決を受けた場合でも、前歴は残ります。
書類送検は、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐという正式な捜査手続きの一部です。したがって、書類送検されたという事実は、捜査対象になった記録、すなわち「前歴」として警察や検察の内部資料に残ることになります。
この前歴は、戸籍や住民票に記載されることはなく、一般の企業や個人が照会することもできません。日常生活において直接的な不利益が生じることはほとんどありません。しかし、万が一将来、別の事件で捜査の対象となった場合には、この前歴が参照され、捜査機関から「反省していないのではないか」と厳しい目で見られたり、処分が重くなる方向に影響したりする可能性は否定できません。
4. 書類送検の前後の流れ
刑事事件の手続きは、多くの方にとって未知の世界であり、次に何が起こるのか分からないという状況が、不安を一層大きくします。ここでは、事件が発生してから書類送検を経て、最終的な処分が決まるまでの一連の流れを、時系列に沿って具体的に解説します。
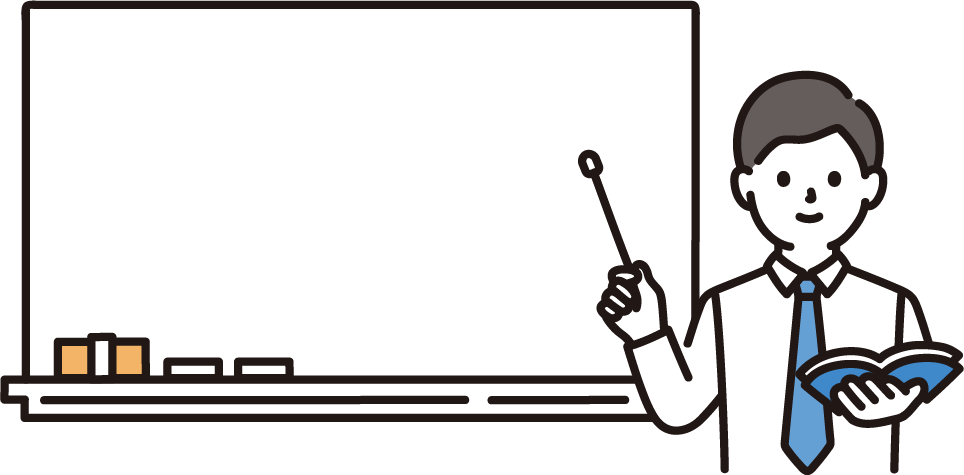
4-1. 警察の取り調べが行われる
すべての刑事事件は、犯罪の発生から始まります。被害者からの被害届の提出、目撃者からの通報、あるいは警察官による現認などによって、警察は事件を認知し、捜査を開始します。
捜査の過程で、防犯カメラの映像や聞き込みなどから被疑者が特定されると、警察は被疑者に連絡を取り、警察署への出頭を求めます。これが「任意同行」や「任意での事情聴取」と呼ばれるものです。在宅事件の場合、この任意での取り調べが捜査の中心となります。被疑者は、警察官から事件に関する詳細な聴取を受け、その内容をまとめた「供述調書」が作成されます。
4-2. 書類送検される
警察は、被疑者の取り調べだけでなく、被害者や目撃者からの事情聴取、現場検証、証拠品の分析など、多角的な捜査を行います。これらの捜査活動を通じて収集した証拠や作成した調書などを一つのファイルにまとめます。
警察としての捜査が一通り完了したと判断されると、この事件ファイル一式を管轄の検察庁に送ります。この手続きが「書類送検」です。この際、警察官から「この事件を検察庁に送ります」といった告知がなされるのが一般的です。この瞬間から、事件の担当は警察から検察官へと移ります。
4-3. 検察から呼び出され取り調べが行われる
書類送検を受けた検察官は、まず警察から送られてきた捜査記録を精査します。そして、多くの場合、検察官自らが被疑者から直接話を聞くために、検察庁への出頭を求めます。
検察官によるこの取り調べは「検事調べ」と呼ばれ、起訴・不起訴という最終処分を決定するための非常に重要なプロセスです。検察官は、警察の捜査内容に間違いがないか、被疑者の言い分に矛盾はないか、反省の態度はどうかといった点を、独自の視点から厳しくチェックします。呼び出しは一度で終わることもあれば、複数回にわたることもあります。
4-4. 起訴か不起訴が決まる
検察官は、警察の捜査記録、自ら行った取り調べの内容、被害者の処罰感情、示談の有無など、事件に関するあらゆる事情を総合的に考慮し、最終的な処分を決定します。この決定が、事件の行方を決定づける最大の分岐点です。
- 起訴処分検察官が「刑事裁判にかけるべき」と判断した場合、「起訴」します。起訴には、公開の法廷で審理を行う「公判請求」と、書面審理のみで罰金刑を求める「略式命令請求(略式起訴)」があります。
- 不起訴処分検察官が「裁判にかける必要はない」と判断した場合、「不起訴」となります。不起訴の理由にはいくつかありますが、代表的なものは以下の通りです。
- 嫌疑不十分:犯罪を証明する証拠が足りない場合。
- 起訴猶予:犯罪の嫌疑は十分にあるものの、犯行が軽微である、被疑者が深く反省している、被害者との示談が成立しているといった事情を考慮し、あえて起訴を見送る場合。実務上、不起訴処分の中で最も多いのがこの起訴猶予です。
4-5. 裁判に出席する
検察官によって起訴された場合、被疑者は「被告人」という立場になり、刑事裁判を受けることになります。裁判所から「起訴状」という書類が送達され、裁判の日時が指定されます。
正式な裁判(公判)では、法廷で検察官が犯罪事実を証明し、弁護人が被告人のために反論や有利な事情の主張を行います。裁判官は、双方の主張と証拠に基づいて、最終的に有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を科すのか(判決)を言い渡します。
5. 書類送検によるリスク
逮捕・勾留という身体拘束を伴わない書類送検は、一見するとリスクが低いように感じられるかもしれません。しかし、その裏には見過ごすことのできない、いくつかの重大なリスクが潜んでいます。これらのリスクを正しく認識することが、ご自身の未来を守る第一歩となります。
5-1. 起訴されて有罪になり刑罰が科される可能性がある
最大のリスクは、言うまでもなく起訴され、有罪判決を受けて前科がつくことです。前述の通り、刑法犯で36.9%、特別法犯で45.4%という決して低くない確率で起訴されています。
さらに深刻なのは、日本の刑事裁判における有罪率の高さです。一度起訴されてしまうと、その有罪率は99.9%とも言われており、無罪を勝ち取るのは極めて困難です。つまり、「起訴されること」が、事実上「有罪判決を受け、前科がつくこと」とほぼ同義になっているのが現状です。罰金刑であっても前科はつきますし、事件の内容によっては執行猶予付きの懲役刑や、最悪の場合、実刑判決が下される可能性もゼロではありません。

5-2. 起訴・不起訴の決定までが長い
在宅事件である書類送検のもう一つの大きなリスクは、捜査期間の長期化です。逮捕・勾留されている身柄事件では、法律で最大23日間という厳格な時間制限が設けられており、その期間内に検察官は起訴・不起訴を決定しなければなりません。
しかし、在宅事件にはこのような時間制限がありません。検察官は、事件の公訴時効(犯罪が終わった時から一定期間が経過すると起訴できなくなる制度)が完成するまで、いつでも起訴することが可能です。そのため、事件によっては、書類送検から数ヶ月、場合によっては1年以上もの間、起訴されるのかどうかわからない、という宙ぶらりんの状態で待たされることがあります。この先の見えない不安な日々が続くこと自体が、ご本人やご家族にとって計り知れない精神的負担となります。
5-3. 国選弁護人がつかない
刑事手続きにおいて、弁護士のサポートは極めて重要です。しかし、書類送検された段階では、原則として国選弁護人(国が費用を負担して選任する弁護士)のサポートを受けることができません。
国選弁護人制度は、被疑者が逮捕され、勾留状が発付された後、あるいは起訴された後でなければ利用できない仕組みになっているからです。在宅事件の被疑者は、身体拘束をされていないため、この条件に当てはまりません。
これは、被疑者にとって非常に不利な状況を意味します。なぜなら、不起訴処分を勝ち取るための最も重要な活動(被害者との示談交渉など)は、検察官が起訴・不起訴を決定する前の、この捜査段階に集中するからです。最も弁護士の助けが必要な、結果を左右する極めて重要な時期に、国からの公的な援助はないのです。したがって、この段階で専門的なサポートを受け、有利な結果を目指すためには、自ら私選弁護人(自分で依頼する弁護士)を探し、依頼する以外に方法はありません。
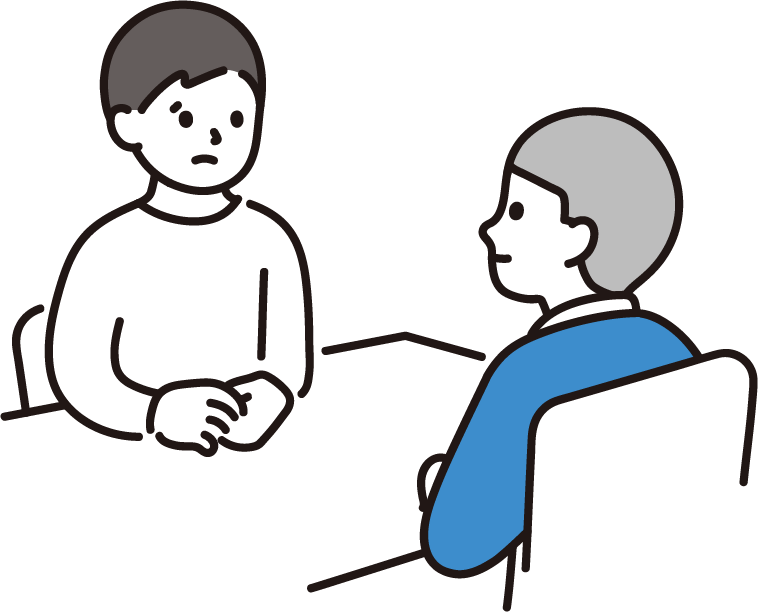
5-4. 会社にバレる可能性はゼロではない
在宅事件であれば、日常生活を続けられるため、会社に知られずに事件を終えられる可能性は高いです。警察や検察が、正当な理由なく勤務先に連絡することも基本的にはありません。
しかし、会社に発覚するリスクが全くないわけではありません。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 事件が職場に関連する場合:会社の備品を盗んだ(窃盗)、経費を不正利用した(横領・詐欺)など、事件そのものが会社を舞台としている場合、捜査の過程で会社への聞き取りや資料提出の要求が行われ、発覚は避けられません。
- 捜査上の必要性がある場合:事件に関係する証拠が職場にある場合など、家宅捜索ならぬ「会社捜索」が行われる可能性があります。
- 実名報道:事件の社会的な注目度が高い場合や、被疑者が公務員や有名企業の社員である場合などに、実名で報道され、会社に知られてしまうことがあります。
- 裁判への出廷:起訴されて裁判が始まると、平日の昼間に裁判所へ出廷する必要が出てきます。頻繁に会社を休むことで、不審に思われ、結果的に知られてしまう可能性があります。
一度会社に知られてしまうと、就業規則によっては、譴責、減給、出勤停止、あるいは最も重い懲戒解雇といった処分を受けるリスクがあります。
6. 書類送検されたときのポイント
書類送検されたという事実は、重く受け止めなければなりませんが、絶望する必要は全くありません。この段階からでも、ご自身の行動次第で、その後の展開を良い方向に導くことは十分に可能です。ここでは、書類送検された場合に取るべき、具体的で重要なポイントを3つご紹介します。
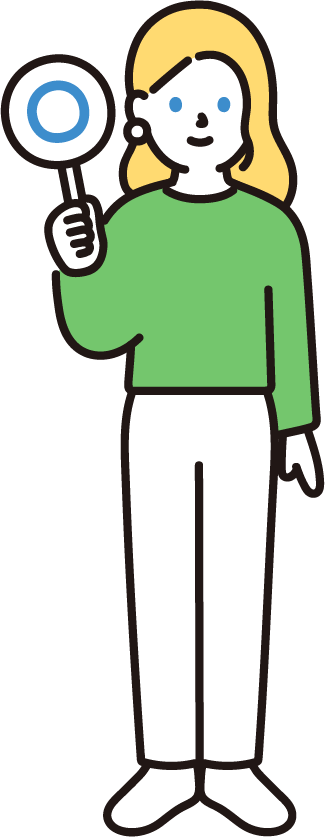
6-1. 検察の呼び出しには誠実に対応する
書類送検後、検察官からの呼び出しは必ずあるものと考えてください。この呼び出しへの対応は、検察官があなたに対して抱く心証を大きく左右します。
まず、指定された日時に必ず出頭することが大前提です。正当な理由なく無視したり、無断で欠席したりすれば、「反省していない」「逃亡のおそれがある」と見なされ、それまで在宅だったにもかかわらず、逮捕状を請求されるという最悪の事態を招きかねません。
そして、取り調べの際には、誠実な態度で臨むことが重要です。聞かれたことに対して、正直に、そして反省の意を示しながら話す姿勢は、検察官に良い印象を与えます。もちろん、やってもいないことまで認める必要はなく、憲法で保障された黙秘権も行使できますが、横柄な態度や嘘の供述は厳に慎むべきです。この「誠実な対応」が、起訴猶予という有利な処分に繋がる一つの要素となります。
6-2. 刑事事件に強い弁護士に相談する
これが最も重要かつ効果的な行動です。前述の通り、書類送検の段階では国選弁護人はつきません。つまり、法律の専門家である弁護士の助けを借りずに、たった一人で屈強な捜査機関(警察・検察)と対峙しなければならないのです。
刑事事件を専門とする弁護士に依頼することで、以下のような多大なメリットが得られます。
- 的確な見通しの提示:あなたの事件が今後どうなる可能性が高いのか、豊富な経験に基づいて的確な見通しを示してくれます。これにより、先の見えない不安が軽減されます。
- 取り調べへの対策:検察官からの取り調べにどう対応すべきか、具体的なアドバイスを受けられます。不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。
- 検察官との交渉:弁護士が代理人として検察官と直接交渉し、あなたに反省の情があることや、示談が成立したことなど、有利な事情を法的な観点から主張し、不起訴処分を求めます。
- 精神的な支え:一人で抱え込まずに済むという安心感は、計り知れないほど大きいものです。
できる限り早く、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談することが、最善の結果を得るための鍵となります。
6-3. 示談交渉を成功させる
被害者がいる犯罪の場合、被害者との示談(じだん)を成立させることが、不起訴処分を勝ち取るための最も有効な手段と言っても過言ではありません。
示談とは、加害者が被害者に対して真摯に謝罪し、示談金を支払うことで、被害によって生じた損害を賠償し、精神的な苦痛を和らげ、当事者間で事件を解決することです。被害者から「加害者を許します」「厳しい処罰は望みません」という意思(宥恕:ゆうじょ)が示された示談書を検察官に提出できれば、検察官が「当事者間で解決済みならば、国が刑罰を科す必要性は低い」と判断し、起訴猶予となる可能性が飛躍的に高まります。
しかし、加害者本人が直接被害者と交渉するのは、現実的にほぼ不可能です。警察は加害者に被害者の連絡先を教えてくれませんし、被害者も加害者と直接会うことを拒絶するのが普通です。ここで弁護士の存在が不可欠になります。弁護士であれば、検察官を通じて被害者の連絡先を入手し、加害者の代理人として冷静かつ円滑に示談交渉を進めることができます。
また、示談金の額も重要です。示談金に法的な決まりはありませんが、事件の種類ごとにおおよその相場が存在します。弁護士は、過去の事例に基づき、適正な示談金額を判断することができます。なお、以下の示談金は、あくまでも一般的な相場です。必ず次の金額で解決できるというわけではありませんのでご注意ください。
| 罪名 | 示談金の一般的な相場 | 備考 |
| 暴行罪 | 10万円~30万円 | 治療費は別途。怪我がない場合。 |
| 傷害罪 | 30万円~100万円以上 | 治療費や休業損害は別途。全治期間や後遺症の有無により大きく変動します。 |
| 窃盗罪 | 被害額 + 10万円~30万円の慰謝料 | 被害品の返還有無や被害額の大小によります。 |
| 痴漢(迷惑行為防止条例違反) | 20万円~50万円 | 愛媛県迷惑行為防止条例第4条などが根拠。行為の態様や場所、被害者の処罰感情で変動します。 |
| 盗撮(性的姿態等撮影罪) | 10万円~50万円 | 撮影場所、被害者の精神的苦痛の度合いによります。 |
示談交渉は、不起訴処分を獲得するための最重要活動です。これを成功させるためにも、刑事弁護の専門家である弁護士への依頼が強く推奨されます。
7. まとめ
この記事では、「書類送検」という手続きについて、その意味から始まり、前後の流れ、伴うリスク、そして採るべき対応策までを詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 書類送検は事件の終わりではない:逮捕されなかったとしても、それは捜査が検察官の手に移り、本格的な処分の検討が始まる合図です。決して楽観視はできません。
- 前科と前歴は違う:書類送検されただけでは「前科」はつきませんが、捜査対象になったという「前歴」は残ります。前科がつくのは、起訴され、裁判で有罪判決が確定した場合です。
- 不起訴処分の獲得が最大の目標:起訴されてしまえば、極めて高い確率で有罪となり前科がつきます。したがって、検察官が起訴・不起訴を判断する前の段階で、不起訴処分を目指す弁護活動を行うことが何よりも重要です。
- 弁護士への相談が不可欠:在宅事件では国選弁護人がつかないため、自ら私選弁護人を依頼しない限り、法律の専門家の助けを得られません。被害者との示談交渉を含め、有利な結果を導くためには、刑事事件に精通した弁護士のサポートが不可欠です。
警察から連絡が来たとき、そして書類送検されると告げられたとき、あなたの心は深い不安と孤独感に苛まれていることでしょう。しかし、あなたは一人でこの困難に立ち向かう必要はありません。正しい知識を持ち、適切なタイミングで専門家の助けを借りることで、道は開けます。
裁判所から起訴状が届いた方はもちろん、警察から連絡があり今後の手続きに不安を感じている方は、お早めにnac刑事法律事務所にご相談ください。私たちは、あなたの不安に寄り添い、最善の解決に向けて全力でサポートします。
