2025年7月5日
盗撮とは?抵触する法令や盗撮の構成要件、対応方法について解説
「盗撮をしてしまったかもしれない」「これからどうなるのだろう」と、大きな不安を抱えてこのページに辿り着いた方もいらっしゃるかもしれません。
スマートフォンの普及により、盗撮は誰にとっても身近な犯罪となり、その法的状況は近年大きく変化しています。
この記事では、あなたの不安に寄り添い、現状を正しく理解していただくための情報を提供します。
コラム作成者の紹介
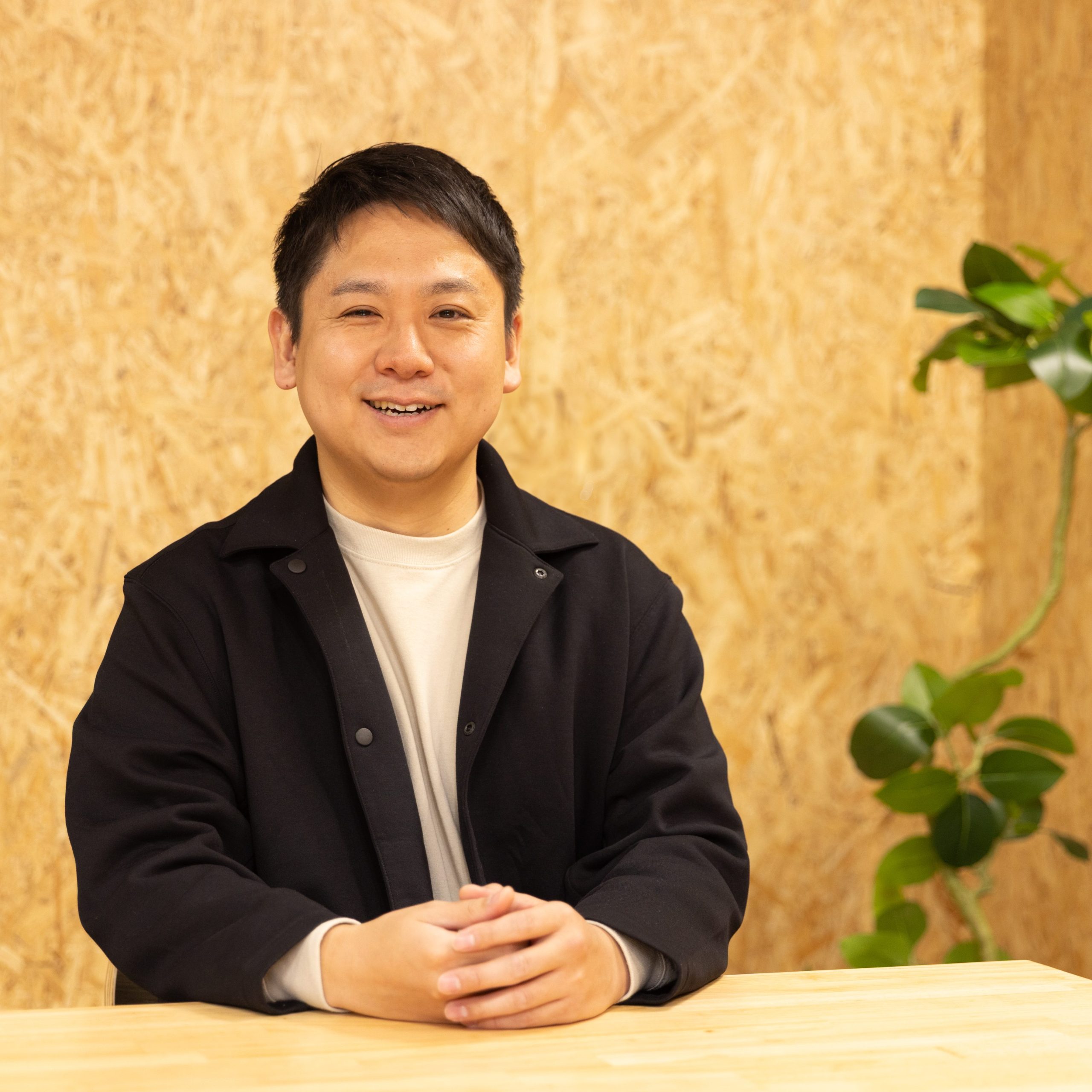
愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
- 盗撮を取り巻く法律は複雑です。 2023年に施行された新しい法律「撮影罪」に加え、以前からある都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法など、複数の法律が関係し、それぞれ成立する条件が異なります。
- 処罰は刑事罰だけではありません。 罰金や懲役だけでなく、事件が職場や学校に知られることで、解雇や退学、資格の剥奪といった、人生を大きく左右する事態に発展する可能性があります。
- しかし、早期の適切な対応が未来を左右します。 特に、被害者の方との示談交渉など、迅速に行動を起こすことで、逮捕を回避したり、不起訴処分を獲得したりできる可能性は十分にあります。
この記事を通じて、まずはご自身の状況を冷静に把握し、一人で抱え込まずに専門家へ相談するという第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

1. 盗撮とは
一般的に「盗撮」とは、相手の同意なく、ひそかに身体や下着などを撮影する行為を指します。
具体的には、スカートの中を撮影する行為や、トイレ、更衣室、お風呂場といった通常は衣服を身に着けていない場所で、プライバシーを侵害し、相手に性的な羞恥心や不安を与えるような撮影行為がこれにあたります。
重要なのは、法律上「盗撮罪」という名前の単一の犯罪が存在するわけではないという点です。
実際の事件では、行為の態様や場所、被害者の年齢などに応じて、後述する複数の法令が適用されることになります。
2. 盗撮に抵触する法令
盗撮行為は、一つの行為が複数の法律や条例に触れる可能性がある、非常に複雑な分野です。
この複雑さこそが、ご自身での判断を難しくし、専門家である弁護士への相談を必要とする大きな理由です。
主に、2023年に新設された「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」、各都道府県が定める「迷惑防止条例」、そして古くからある「軽犯罪法」が基本的な規制となります。
さらに、状況によっては盗撮のために他人の敷地に立ち入ることで「住居侵入罪」、被害者が18歳未満であれば「児童ポルノ禁止法」といった、より重い犯罪が成立することもあります。
これらの法令は、それぞれ罰則や時効が異なるため、どの法律が適用されるかによって、その後の対応や見通しが大きく変わってきます。
| 法令名 | 主な処罰対象行為 | 法定刑 | 公訴時効 |
| 性的姿態撮影等処罰法(撮影罪) | 性的な部位や下着等のひそかな撮影、同意のない状態での撮影など | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 |
| 愛媛県迷惑行為防止条例 | 公共の場所等での卑わいな撮影行為、のぞき見など | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 |
| 軽犯罪法 | 正当な理由なく、住居や浴場などをひそかにのぞき見る行為 | 拘留(1日以上30日未満)又は科料(1,000円以上1万円未満) | 1年 |
| 刑法(住居侵入罪) | 盗撮目的で、正当な理由なく他人の住居や建造物に侵入する行為 | 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童ポルノ禁止法 | 18歳未満の者の性的な姿態をひそかに撮影する行為(児童ポルノ製造) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 |
2-1. 撮影罪とは
「撮影罪」とは、正式名称を「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称:性的姿態撮影等処罰法)といい、令和5年(2023年)7月13日に施行された新しい法律です。
この法律が作られた背景には、スマートフォンの普及などにより盗撮被害が深刻化し、これまでの都道府県ごとの迷惑防止条例だけでは対応が不十分であるという社会的な認識がありました。
そこで、全国一律の基準で盗撮行為を厳しく取り締まるために、この法律が制定されたのです。
法務省の解説によれば、この法律の目的は「意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益を守るため」とされています。
つまり、単に撮影する行為だけでなく、それによって撮影された画像を他人に提供したり、保管したり、インターネットでライブ配信したりする一連の行為も処罰の対象とし、被害の発生と拡大を防ぐことを目指しています。
2-1.1. 撮影罪と盗撮罪の違い
よく「盗撮罪」という言葉を耳にしますが、これは法律上の正式な名称ではありません。
一般的に盗撮と呼ばれる行為の多くを処罰するために新しく作られた犯罪の正式名称が「性的姿態等撮影罪」、通称「撮影罪」です。

つまり、「盗撮罪」は一般的な呼び名であり、法的な議論や手続きにおいては「撮影罪」または「性的姿態等撮影罪」という言葉が使われると理解しておくとよいでしょう。
このコラムでも、新しい法律については「撮影罪」として解説を進めます。
2-2. 迷惑防止条例とは
撮影罪が全国一律の法律であるのに対し、「迷惑防止条例」は各都道府県が独自に定めている条例です。
愛媛県では「愛媛県迷惑行為防止条例」がこれにあたります。
撮影罪が新設された後も、この迷惑防止条例が適用される場面は依然として存在します。
特に、愛媛県内での行為については、この条例の内容を正確に理解することが不可欠です。
愛媛県迷惑行為防止条例では、第4条で「卑わいな行為の禁止」を定めており、盗撮に関連する行為もここで規制されています。
具体的には、公共の場所や公共の乗り物において、他人の衣服で覆われている下着や身体を撮影する目的でカメラを向けたり、住居や浴場、便所、更衣室といった場所で、人が衣服を身に着けていない状態の姿態を撮影する目的でカメラを向けたりする行為が禁止されています。
このように、全国的な法律と地域に根差した条例が重なり合って規制を形成しているため、どの法律が適用されるかの判断には専門的な知識が求められます。
2-3. 軽犯罪法とは
「軽犯罪法」は、社会の秩序を維持するために、比較的軽微な違反行為を罰する法律です。
盗撮との関連では、特に「のぞき行為」がこの法律に触れる可能性があります。
軽犯罪法では、以下の行為が禁止されています。
軽犯罪法 第1条第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
この条文は、カメラなどを使わない「のぞき見」行為を対象としています。
もし撮影まではしていなくても、トイレや更衣室をのぞき見た場合、この法律に違反する可能性があります。
罰則は拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)と他の法律に比べて軽いものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
2-4. 住居侵入罪とは
盗撮行為は、しばしば他の犯罪と結びつきます。その典型が「住居侵入罪」です。
例えば、アパートの共用廊下や他人の家の敷地内に、盗撮する目的で無断で立ち入った場合、盗撮行為そのものとは別に住居侵入罪が成立します。
この犯罪は刑法で定められています。
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一つの行為が二つの犯罪(この場合は撮影罪と住居侵入罪)として扱われることを「併合罪」といい、処罰がより重くなる可能性があります。
盗撮事件では、この住居侵入罪が同時に成立していないかという点も、非常に重要な検討事項となります。
2-5. 児童ポルノ禁止法とは
盗撮行為の中で、最も深刻な事態となるのが、被害者が18歳未満の「児童」である場合です。
この場合、行為は単なる盗撮ではなく、「児童ポルノの製造」という極めて重い犯罪にあたる可能性があります。
この行為を規制するのが「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称:児童ポルノ禁止法)です。
この法律では、「児童」を18歳に満たない者と定義しています。
そして、ひそかに児童の性的な姿態を撮影する行為は、児童ポルノを「製造」したものとみなされます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第4項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
「第二項と同様とする」とあるため、罰則は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
被害者が未成年であるという事実は、事件の悪質性を格段に高め、極めて厳しい処分が予想されます。
3. 盗撮の構成要件
ある行為が犯罪として成立するためには、法律で定められた「構成要件」と呼ばれる条件をすべて満たす必要があります。
ここでは、盗撮に関する主要な犯罪である「撮影罪」と「迷惑防止条例違反」の構成要件を詳しく見ていきましょう。
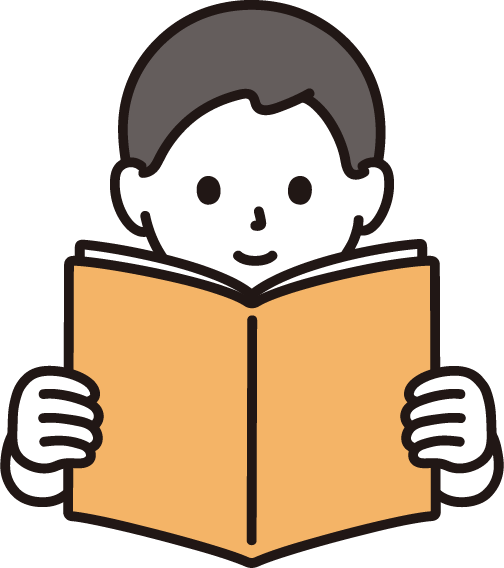
3-1. 撮影罪の場合
新しい法律である撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立するためには、主に以下の4つの要素が必要です。
- 何を(客体): 「性的姿態等」を撮影の対象としていること。「性的姿態等」とは、法律で具体的に定義されています。
- 人の性的な部位(性器、臀部、胸部など)や、それを覆っている下着
- 性交やわいせつな行為が行われている際の人の姿
- どうやって(実行行為): 上記の「性的姿態等」を「撮影」すること。実際に撮影に成功しなくても、撮影しようとする行為(未遂)も罰せられます。
- どのような状況で(行為状況): 以下のいずれかの方法で撮影が行われること。
- ひそかに撮影する: いわゆる典型的な盗撮です。
- 相手の同意がない状態で撮影する: 暴行や脅迫を用いたり、相手が薬物やアルコール、睡眠などで正常な判断ができない状態に乗じて撮影する場合です。相手が撮影に気づいていても、自由な意思で同意していなければ犯罪になります。
- 相手をだまして撮影する: 「健康診断のため」などと嘘をついて、性的な撮影ではないと誤信させて撮影する場合です。
- 相手が16歳未満の年少者である場合に撮影する: 相手が16歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、正当な理由なく性的な姿態を撮影すれば犯罪となります。特に、相手が13歳以上16歳未満の場合は、撮影者が5歳以上年長である場合に処罰対象となります。
- 正当な理由がないこと:撮影に「正当な理由」がないことが要件です。法務省の解説によれば、例えば「医師が医療行為として患者の姿を撮影する場合」などは正当な理由にあたるとされていますが、これは非常に限定的なケースです。個人の性的好奇心を満たすための撮影が正当化されることはありません。
3-2. 迷惑防止条例の場合
次に、愛媛県迷惑行為防止条例が適用される場合の構成要件を見ていきましょう。
- どこで/誰に(場所・対象):
- 「公共の場所」(道路、公園、駅など)や「公共の乗物」(電車、バスなど)にいる人に対して行われること。
- または、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にいる人に対して行われること。
- 何を(客体):
- 衣服などで覆われている「下着または身体」
- または、衣服を身に着けていない状態の「姿態」
- どうやって(実行行為):
- 上記を下着等の上から、あるいは直接、見たり、撮影したりする行為。カメラを向けるだけでも処罰の対象となり得ます。
- どのような方法で(行為態様):
- 「その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法」で行われること。
この「性的羞恥心を著しく害し」という部分は、客観的に判断されますが、個別の事案によって解釈の幅があるため、弁護士による法的な主張が重要になるポイントです。
4. 盗撮で処罰される具体例
法律の条文だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、実際にどのような行為が盗撮として処罰されるのか、具体的な例を挙げます。
- 駅のエスカレーターや階段で、前を歩く女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影する行為。
- 商業施設のトイレや会社の女子トイレに小型カメラを設置し、利用者を撮影する行為。
- 他人の住むマンションの敷地内に侵入し、窓から部屋の中にいる女性の着替えの様子などを撮影する行為。
- スポーツジムや衣料品店の試着室(更衣室)で、仕切りの上や下からカメラを向けて撮影する行為。
- ペン型や靴に仕込むタイプの特殊なカメラを使い、公共の場所で不特定多数の女性を撮影する行為。
これらの行為は決して稀なものではなく、実際に多くの事件が発生しています。
警察庁が公表した「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況」によると、撮影罪(ひそかに撮影)の検挙件数のうち、発生場所として最も多いのは「ショッピングモール等商業施設」(35.4%)、次いで「駅構内」(22.0%)となっています。
また、迷惑防止条例違反では、「通常衣服を着けない場所(住居、便所、浴場、更衣室等)」が36.5%と最も多く、私的な空間での被害が深刻であることがわかります。
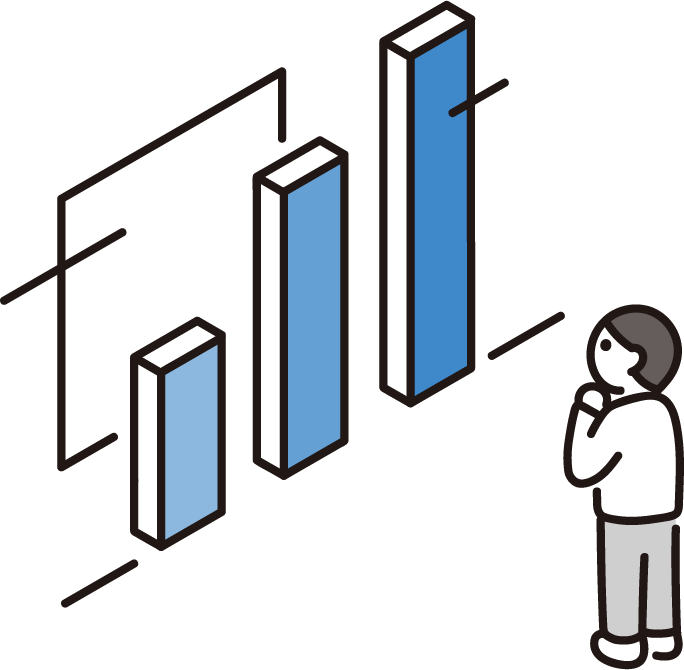
これらの統計は、警察がどのような場所を重点的に警戒しているかを示唆しており、軽い気持ちで行った行為が発覚するリスクが非常に高いことを物語っています。
5. 盗撮における罰則
盗撮行為に科される罰則は、どの法律が適用されるかによって大きく異なります。ここでは、主要な法律の罰則を具体的に確認します。
5-1. 撮影罪の罰則
令和5年(2023年)に施行された性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為だけでなく、撮影した画像の拡散行為などにも厳しい罰則が設けられています。
- 性的姿態等撮影罪(撮影する行為)3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的姿態撮影等処罰法 第2条)
- 性的影像記録提供等罪(撮影した画像などを提供・陳列する行為)
- 特定または少数の人に提供した場合:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(同法 第3条1項)
- 不特定または多数の人に提供・公然と陳列した場合:5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法 第3条2項)
- 性的影像記録保管罪(提供する目的で画像を保管する行為)2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(同法 第4条)
このように、特に撮影した画像をインターネット上などで公開した場合は、非常に重い罪に問われることがわかります。
5-2. 迷惑防止条例の罰則
愛媛県迷惑行為防止条例における盗撮関連行為の罰則は以下の通りです。
愛媛県迷惑行為防止条例 第16条
- 第4条(中略)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
通常は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですが、繰り返し盗撮行為を行っている「常習者」と認められた場合は、懲役刑の上限が2年に引き上げられます。
撮影罪と比較すると罰則は軽いものの、決して軽視できるものではありません。
6. 盗撮で逮捕されるケースとされないケース
盗撮の疑いをかけられたからといって、必ずしも全員が逮捕されるわけではありません。
警察が逮捕に踏み切るかどうかは、法律で定められた要件に基づいて判断されます。

6-1. 盗撮で逮捕されるケース
逮捕には、犯行現場で身柄を拘束される「現行犯逮捕」と、後日、裁判官が発付する逮捕状に基づいて逮捕される「通常逮捕」があります。
盗撮事件で逮捕に至る主な理由は、刑事訴訟法で定められている「逃亡のおそれ」と「罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ」が認められる場合です。
- 現行犯逮捕されるケース盗撮事件で最も多いのがこのケースです。被害者本人や周囲の目撃者にその場で取り押さえられた場合などが該当します。犯行と犯人が明白であるため、逮捕の要件を満たしやすい状況です。
- 後日逮捕(通常逮捕)されるケースその場では発覚しなくても、防犯カメラの映像や目撃者の証言などから後日犯人として特定され、逮捕状が請求されるケースです。以下のような事情があると、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕されやすくなります。
- 犯行を否認している場合
- 住所不定であったり、連絡が取れなくなったりした場合
- スマートフォンなどの証拠品の提出を拒むなど、捜査に非協力的な態度をとった場合
6-2. 盗撮で逮捕されないケース
一方で、盗撮の疑いがあっても逮捕されず、「在宅事件」として捜査が進められることもあります。
これは、警察が「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がないと判断した場合です。
- 逮捕されない可能性のある事情
- 定まった住居があり、安定した職業に就いている。
- 家族が身元引受人になることを約束している。
- 犯行を素直に認め、深く反省している。
- 任意での事情聴取の求めに素直に応じ、スマートフォンなどの証拠品も自ら提出するなど、捜査に全面的に協力している。
- 自ら警察署に出頭(自首)した場合。
重要なのは、逮捕されないことと、無罪になることは全く違うということです。
在宅事件であっても捜査は継続し、証拠が揃えば起訴されて刑事裁判になる可能性は十分にあります。
7. 盗撮の時効
犯罪には「公訴時効」という制度があり、犯罪行為が終わってから一定期間が経過すると、検察官は起訴できなくなります。
つまり、国が処罰する権利が消滅するのです。
盗撮関連犯罪の公訴時効は、適用される法律によって異なります。
- 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反):3年
- 愛媛県迷惑行為防止条例違反:3年
- 軽犯罪法違反:1年
時効期間は、犯罪行為が終わった時からカウントが始まります。
例えば、撮影罪や迷惑防止条例違反の場合、盗撮行為から3年間は、いつ後日逮捕されてもおかしくない、という不安定な状態が続くことになります。
「すぐには捕まらなかったから大丈夫」と安易に考えるのは非常に危険です。
8. 盗撮してしまった場合の対応方法
もし盗撮行為をしてしまい、今後のことが不安でたまらないという状況であれば、ただ時間が過ぎるのを待つのは最善の策ではありません。
ご自身の将来への影響を最小限に抑えるために、積極的に取るべき行動があります。
8-1. 自首をする
もし、まだ捜査機関に犯人として特定されていない段階であれば、「自首」をすることが考えられます。
自首とは、自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねることをいいます。
自首には、法律上および事実上の大きなメリットがあります。
- 法律上のメリット刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており、裁判になった場合に刑が軽くなる可能性があります。
- 事実上のメリット自ら罪を申告する行為は、反省の意思や逃亡しない意思の表れと評価され、逮捕を回避できる可能性を高めます。検察官が起訴・不起訴を判断する際にも、有利な情状として考慮されるでしょう。
ただし、警察がすでに犯人を特定している場合は、自ら出向いても「自首」ではなく「出頭」の扱いとなり、刑を減軽する法律上の効果は得られません。
自首を検討する場合は、タイミングが非常に重要です。
弁護士に相談の上、付き添ってもらって自首することで、手続きをスムーズに進め、取り調べに対しても適切な対応を取ることが可能になります。
8-2. 示談交渉を円滑に進める
盗撮事件のような被害者がいる犯罪において、最も重要な活動が「示談交渉」です。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことで、当事者間で事件を解決する合意をすることです。
示談の成立は、その後の刑事手続きに絶大な影響を与えます。検察官が起訴するかどうかを判断する際、被害者の処罰感情(加害者を罰してほしいという気持ち)を非常に重視します。
示談が成立し、被害者から「許す」という意思(宥恕)が得られれば、検察官は「当事者間で解決が図られており、あえて国が刑罰を科す必要性は低い」と判断し、不起訴処分(起訴猶予)とする可能性が非常に高くなります。
しかし、加害者本人が直接被害者と交渉することは、事実上不可能です。
警察は被害者の連絡先を教えてくれませんし、無理に接触しようとすれば証拠隠滅や脅迫とみなされ、かえって状況を悪化させかねません。
弁護士であれば、検察官を通じて被害者の連絡先を入手し、加害者の代理人として冷静かつ丁寧な交渉を行うことができます。
被害者の心情に最大限配慮しながら、適切な示談成立を目指すためには、弁護士のサポートが不可欠です。
9. 盗撮によって人生が変わるリスク
盗撮事件で有罪判決を受けると、その影響は罰金や刑務所に行くだけにとどまりません。
社会生活の様々な場面で、深刻な不利益を被るリスクがあります。

- 職場での解雇・懲戒処分私生活での犯罪であっても、会社の就業規則によっては懲戒処分の対象となります。特に、公務員の場合はその影響が甚大です。国家公務員法や地方公務員法では、禁錮以上の刑(執行猶予付き判決を含む)が確定すると、自動的に失職することが定められています。また、人事院が定める「懲戒処分の指針について」では、「盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする」と明記されており、有罪判決に至らなくても厳しい処分が下される可能性があります。
- 資格の剥奪医師や教師など、特定の資格を要する職業の場合、罰金以上の刑に処されると、資格の停止や剥奪といった行政処分を受ける可能性があります。医師法や教育職員免許法には、有罪判決を受けた場合の欠格事由が定められており、職業生命そのものが脅かされる事態となり得ます。
- 家族や社会生活への影響逮捕されれば実名で報道されるリスクがあり、そうなれば家族や友人、近隣住民に事件のことが知れ渡ってしまいます。前科がつくことで、その後の就職や結婚など、人生の様々な場面で計り知れない障害となる可能性があります。
これらの深刻なリスクを回避するためには、刑事事件化の初期段階で弁護士に相談し、不起訴処分の獲得を目指すことが何よりも重要です。
10. 盗撮に関するよくある質問
10-1. 盗撮は逮捕されるか
必ず逮捕されるとは限りませんが、可能性は十分にあります。
特に、犯行現場で取り押さえられた場合(現行犯逮捕)や、犯行を否認して逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、逮捕される可能性が高くなります。
一方で、素直に犯行を認め、捜査に協力すれば、逮捕されずに在宅事件として扱われることもあります。
10-2. 後日逮捕されることもあるか
はい、あります。
犯行現場から立ち去ることができても、防犯カメラの映像などから身元が特定されれば、後日、警察が逮捕状を持って自宅に来る可能性があります。
犯罪の公訴時効が成立するまでは、そのリスクは消えません。
10-3. 盗撮は通報されることもあるか
はい、非常に多くあります。被害者自身が警察や駅員に通報するケースのほか、周囲にいた人が不審な動きに気づいて通報するケースも少なくありません。
スマートフォンが普及した現代では、誰もが盗撮行為を目撃し、通報する可能性があります。
10-4. 下着が写らなければ逮捕されないか
いいえ、そんなことはありません。新しい「撮影罪」では、下着だけでなく臀部や胸部といった「性的な部位」も撮影対象に含まれます。
また、愛媛県の迷惑防止条例などでは、実際に撮影に成功しなくても、撮影する目的でカメラを向ける行為自体が処罰の対象となりえます。
つまり、「未遂」でも犯罪は成立するのです。下着が写っているかどうかは、処罰の重さを判断する一要素に過ぎません。
まとめ

ここまで、盗撮という行為がどのような法律に触れ、どのような結果を招く可能性があるのかを詳しく解説してきました。
ご理解いただけたように、盗撮は決して軽い犯罪ではなく、2023年の法改正により、社会全体としてより厳しく対処する姿勢が明確に示されています。
一つの過ちが、ご自身の仕事、家庭、そして将来のすべてに深刻な影響を及ぼす可能性があります。
今、この記事を読んでくださっているあなたは、計り知れない不安の中にいることでしょう。
しかし、最も危険なのは、その不安から目をそらし、何もしないで時間だけが過ぎていくことです。
盗撮事件は、被害者の方の心の傷を少しでも癒すための示談交渉をはじめとして、早期に適切な弁護活動を行うことで、逮捕や勾留を避け、不起訴処分を獲得できる可能性が十分にある分野です。
不起訴となれば前科はつかず、社会生活への影響を最小限に食い止めることができます。
最初の一歩は、ご自身の状況を法的な観点から正確に把握することです。一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。私たちは、最善の解決策を一緒に見つけ出すお手伝いをします。

