2025年7月8日
その弁護士特約、刑事事件も対象かも?交通事故の加害者が今すぐ知るべき保険の新知識
交通事故の加害者になってしまい、刑事事件の弁護士費用で悩んでいませんか?
交通事故の加害者になってしまい、刑事事件の弁護士費用で悩んでいませんか?
多くの方が「弁護士特約は使えない」と思いがちですが、実はその常識はもう古いかもしれません。
最近、愛媛県内では交通事故が増加傾向にあるとの報道もあり、決して他人事ではありません。
特に自転車が関わる死亡事故や、単独事故の件数が増えているとのことで、誰もが交通事故の当事者になる可能性があります。
全国的に見れば、交通事故の発生件数自体は長期的に減少傾向にありますが、それでも令和4年には年間で30万件以上の人身事故が発生し、多くの方がその後の対応に苦慮されています。
万が一、人身事故の加害者となってしまった場合、被害者の方への民事上の損害賠償だけでなく、ご自身の刑事事件への対応という、重い問題が待ち受けています。
その際、多くの方が頭を悩ませるのが、弁護士に依頼するための費用です。
この記事を読めば、「なぜ加害者の刑事事件でも弁護士特約が使えるケースがあるのか」「ご自身の保険が対象かどうかを確認する具体的な方法」が分かります。
費用の不安を解消し、ご自身とご家族の未来を守るための第一歩を踏み出すことができる可能性があります。
コラム作成者の紹介
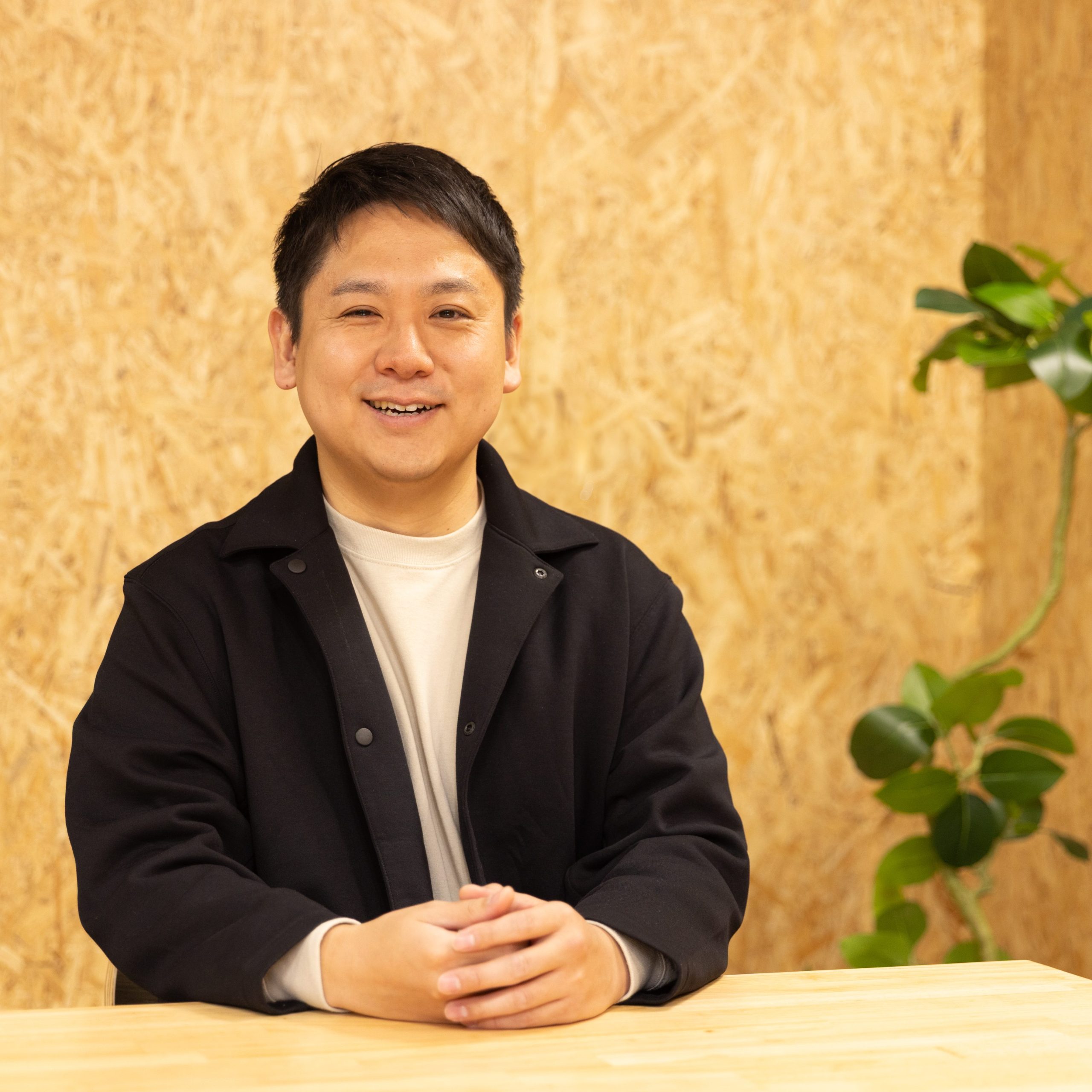
愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
結論:加害者の刑事事件でも弁護士特約は【条件付きで】使える!
まず、最もお伝えしたい結論から申し上げます。
交通事故の加害者となってしまった場合でも、ご自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約を、刑事事件の弁護士費用に使える場合があります。
これは、ひと昔前の常識を覆す、非常に重要な情報です。
近年、一部の保険会社の特定の特約では、加害者の刑事事件の弁護士費用も補償の対象となっています。
具体的には、被害者の方が死亡された場合や、ご自身が逮捕・起訴された場合など、特に重大な局面で利用できるケースが増えています。
この事実は、加害者となってしまった方にとって、一条の光となり得ます。
刑事手続きという、精神的にも経済的にも大きな負担がかかる状況において、弁護士のサポートを費用面の心配を軽減しながら受けられる可能性があるからです。
ただし、重要な注意点があります。
それは、全ての保険契約がこの新しい補償範囲に対応しているわけではないということです。
そのため、ご自身が加入している保険の契約内容を正確に確認することが不可欠となります。

なぜ使えるようになった?補償範囲の広い「新しい特約」の登場
「加害者の刑事事件では弁護士特約は使えない」という話を聞いたことがあるかもしれません。
それは間違いではありませんでした。かつては、それが常識だったのです。
従来の弁護士費用特約は、その補償範囲が「被害事故における民事上の損害賠償請求」に限定されているものがほとんどでした。
つまり、ご自身が被害者として、相手方に治療費や慰謝料などを請求するために弁護士を依頼する場合にのみ使える、というものでした。
しかし、2019年頃から、保険会社各社が商品の改定を進め、より補償範囲の広い「新しいタイプ」の弁護士費用特約が登場しました。
これらの新しい特約は、従来の「自動車事故限定型」とは異なり、「日常生活・自動車事故型」といった名称で提供されることが多く、自動車事故以外の日常トラブルにも対応できるのが特徴です。
そして、その最も画期的な点が、「対人加害事故に関する刑事事件対応」の費用が補償対象に含まれるようになったことです。
例えば、損保ジャパンの『THE クルマの保険』に付帯できる弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)では、ウェブサイトやパンフレット上で「対人加害事故に関する刑事事件の対応」が補償対象に含まれることが明記されています。
引用元URL: https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/the-kuruma/
この特約では、自動車事故で他人にケガをさせてしまった結果、刑事事件(少年事件を含む)となった場合に、弁護士費用や法律相談費用が支払われるとされています。
このように、保険商品そのものが時代に合わせて進化しているのです。
この変化が、「加害者の刑事事件でも弁護士特約が使える」という新しい常識を生み出しました。
表1:弁護士費用特約の補償範囲の比較
| 補償内容 | 従来の特約(自動車事故限定型など) | 新しい特約(日常生活・自動車事故型など) |
| 主な目的 | 被害事故の民事賠償請求 | 被害事故の民事賠償請求+α |
| 被害者としての民事請求 | 対象 | 対象 |
| 加害者としての刑事弁護 | 対象外 | 対象(※条件付き) |
| 自動車事故以外の日常事故 | 対象外 | 対象 |
あなたの保険は対象?今すぐできる確認3ステップ
ご自身の保険が、この新しいタイプの特約に該当するかどうか。それを知るためには、ご自身で契約内容を確認する必要があります。
不安に思われるかもしれませんが、手順を踏めば決して難しいことではありません。
ここでは、今すぐご自身でできる3つのステップをご紹介します。
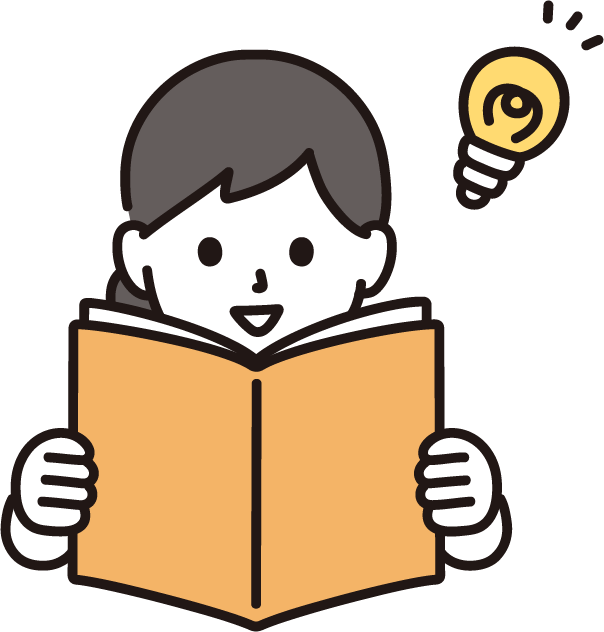
ステップ1:保険証券で「特約の正式名称」を確認する
まず、お手元に自動車保険の保険証券(または保険契約継続証)をご用意ください。
そこに、ご自身が契約している特約の一覧が記載されています。
注目すべきは、特約の「正式名称」です。単に「弁護士費用特約」と書かれているだけの場合もありますが、その名称に「日常生活」や「個人賠償」といった、補償範囲の広さを示唆する言葉が含まれていないかを確認してください。
- 「弁護士費用特約(自動車事故限定)」 → 従来のタイプの可能性が高いです。
- 「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」 → 新しいタイプの可能性が高いです。
名称だけで判断はできませんが、これは重要な手がかりの一つです。
ステップ2:約款(ご契約のしおり)で「補償範囲」を読む
次に、より詳しく内容を確認するために、保険の「約款」や「ご契約のしおり」といった書類に目を通します。
これらの書類は、保険契約時に受け取っているはずですが、見当たらない場合は保険会社のウェブサイトからダウンロードできることも多いです。
書類の中で確認すべきは、「弁護士費用特約」に関するページです。
特に、「保険金をお支払いする場合」といった項目を注意深く読んでください。
その中に、「刑事事件」「被疑者」「刑事弁護費用」といったキーワードに関する記載がないかを探します。
もし、「被保険者が対人事故により刑事事件の被疑者となった場合」や「相手の方が死亡された場合」といった文言があれば、あなたの特約は刑事事件に対応している可能性が非常に高いです。
ステップ3:保険会社・代理店に直接問い合わせる
最も確実で、最終的な確認方法が、ご加入の保険会社または保険代理店に直接電話で問い合わせることです。
約款を読んでもよく分からない場合や、自信が持てない場合は、専門家に直接聞くのが一番です。
問い合わせの際は、事故の状況を正直に伝えた上で、特約が利用できるかを明確に質問しましょう。
その際、以下の質問テンプレートをそのままお使いいただけます。
落ち着いて、正確に状況を伝えることが大切です。
<そのまま使える質問テンプレート>
「先日、人身事故を起こしてしまい、加害者となりました。今後、刑事事件の被疑者として、弁護士に弁護を依頼することを検討しています。私が契約しているこの弁護士費用特約は、その際の弁護士費用に使えますでしょうか?」
もし、担当者から「使えません」と即答された場合でも、すぐに諦める必要はありません。
担当者が古い知識のまま対応していたり、約款の理解が不十分だったりする可能性もゼロではないからです。
その場合は、「約款のどの条項に基づいて利用できないのか、具体的な箇所を教えていただけますか」と、冷静に根拠を尋ねてみましょう。
表2:あなたの保険、3ステップ確認チェックリスト
| ステップ | やること | 確認するポイント |
| ステップ1 | 保険証券を見る | 特約の正式名称に「日常生活」などの言葉があるか |
| ステップ2 | 約款・ご契約のしおりを読む | 「保険金をお支払いする場合」の項目に「刑事事件」「被疑者」などの言葉があるか |
| ステップ3 | 保険会社・代理店に電話する | 上記の質問テンプレートを使って、利用の可否を直接確認する |
【要注意】なぜ「使えない」という古い情報が多いのか?
ここまで読んで、「でも、インターネットで調べたら『加害者は使えない』という情報ばかりだった」と混乱されている方もいらっしゃるかもしれません。その混乱は、もっともです。

その理由は、大きく分けて二つあります。
第一に、かつては全ての弁護士費用特約が、加害者の刑事事件を対象外としていたためです。
そのため、その当時の常識に基づいて書かれたウェブサイトの記事や解説が、今もなおインターネット上に数多く残っています。
情報が更新されないまま、古い情報が検索結果の上位に表示され続けているのが現状です。
第二に、法律や保険商品は、時代と共に変化し続けるという点です。
特に、今回ご説明したような保険商品の改定は、比較的最近(2019年頃)の動きです。
この新しい情報が、まだ社会全体に広く浸透していないため、「使えない」という古い常識の方が根強く残ってしまっているのです。
だからこそ、不確かな情報に惑わされず、ご自身の保険契約という一次情報、そして最新の動向を把握している専門家の情報を確認することが何よりも重要なのです。
交通事故の加害者が直面する法的な現実
弁護士費用特約が使えるかもしれない、という希望が見えてきたところで、次に、なぜ弁護士による刑事弁護がそれほど重要なのかをご説明します。
そのためには、交通事故の加害者が直面する法的な現実を正しく理解する必要があります。

事故直後に課される法的な義務
交通事故を起こしてしまった運転者には、法律によって直ちに果たさなければならない義務が定められています。
これを怠ると、それ自体が重い処罰の対象となります。
具体的には、道路交通法第72条に基づき、以下の措置を講じる義務があります。
- 運転の停止義務:直ちに車両の運転を停止すること。
- 救護義務:負傷者がいる場合、速やかに救護すること(119番通報など)。
- 危険防止措置義務:後続車による二次被害などを防ぐため、道路上の危険を取り除くこと。
- 警察への報告義務:最寄りの警察に、事故の発生日時や場所、死傷者の状況などを報告すること。
これらの義務、特に負傷者の救護を怠って現場を立ち去る行為は、いわゆる「ひき逃げ」(救護義務違反)とされ、最大で懲役10年または罰金100万円という非常に重い罰則が科されます。
問われる可能性のある刑事責任
人身事故を起こした場合、運転者は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に基づき、刑事責任を問われる可能性があります。
多くの場合に適用されるのが、同法の第5条「過失運転致死傷罪」です。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文が示す通り、運転上の不注意によって人を死傷させてしまった場合、懲役刑を含む厳しい刑事罰が科される可能性があるのです。
検察官の判断と弁護活動の重要性
事故を起こしたからといって、全ての人が裁判にかけられ、刑罰を受けるわけではありません。
警察による捜査の後、事件は検察庁に送られ、検察官がその人を裁判にかけるか(これを「起訴」といいます)、かけないか(「不起訴」といいます)を判断します。
実は、交通関係の事件では、「起訴猶予」という不起訴処分になるケースが相当数存在します。
起訴猶予とは、「犯罪の疑いは十分あるが、様々な事情を考慮して、今回は起訴を見送る」という検察官の判断です。
この処分となれば、刑事裁判は開かれず、前科もつきません。
では、どのような事情が考慮されるのでしょうか。そこには、以下のような点が大きく影響します。
- 被害者との示談が成立しているか
- 被害者や遺族に対して、真摯な謝罪と反省の意が示されているか
- 事故の態様や、加害者の過失の程度
- 加害者のこれまでの経歴(前科・前歴の有無など)
ここで、弁護士の役割が極めて重要になります。弁護士は、加害者に代わって被害者側と冷静かつ適切に示談交渉を進めることができます。
また、示談の成立だけでなく、反省文の作成や再発防止策の提示などを通じて、加害者の深い反省の意を検察官に説得的に伝えることができます。
つまり、弁護士による早期の弁護活動は、起訴を回避し、前科がつく事態を防ぐための、最も有効な手段なのです。
この「起訴を回避する」という大きなメリットを考えれば、弁護士費用が、ご自身の未来を守るための重要な投資であることがお分かりいただけるでしょう。
愛媛県の条例と交通安全への意識
最後に、地域的な視点にも触れておきます。愛媛県では「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されており、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。
これは、万が一の事故に備え、加害者の賠償責任と被害者の救済を確保するための措置です。
この条例の存在は、自動車だけでなく、すべての道路利用者が「万が一のリスクに備える」という意識を持つことの重要性を社会全体で共有しようという姿勢の表れと言えます。
ご自身が加入している自動車保険の特約内容を正しく把握し、最大限に活用することもまた、この「備え」の一環と言えるでしょう。
まとめ:あなたの弁護士特約、使えるかもしれません。当事務所が確認からサポートします!
この記事でお伝えしてきた重要なポイントを、最後にもう一度まとめます。

- 近年、交通事故の加害者となってしまった方の刑事事件にも使える、新しいタイプの弁護士費用特約が登場しています。
- ただし、全ての保険契約が対象ではないため、ご自身の保険証券や約款の内容をしっかりと確認することが不可欠です。
- 万が一の際に、起訴を回避し、ご自身の未来を守るためには、早期の段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが極めて重要です。
とはいえ、「自分で保険会社に問い合わせるのは、何だか気が引ける」「約款を読んでみたけれど、専門用語が多くてよく分からない」といった不安を感じていらっしゃる方も多いと思います。
事故後の大変な時期に、慣れない手続きをご自身だけで進めるのは、大変なご負担でしょう。
当事務所では、交通事故の加害者となってしまった方の刑事弁護において、弁護士費用特約を利用したご依頼を多数お受けしております。
この新しいタイプの特約が利用できるかどうか、その確認の段階から、当事務所があなたを全面的にサポートいたします。
ご依頼いただければ、ご自身の保険が使えるかどうかの確認から、その後の保険会社とのやり取りまで、全て弁護士が代理で行うことが可能です。
「自分の保険が使えるか分からない」という、まさにその段階で構いません。
一人で悩みを抱え込まず、まずは一度、お気軽にご相談ください。
費用の不安を解消し、これからの手続きを乗り越えていくための最善の道を、一緒に見つけ出します。

