2025年10月4日
もらい事故で過失割合が10対0!自分の保険会社に連絡は必要?
予期せぬ交通事故に遭われ、大変な思いをされていることと存じます。
特に、ご自身に全く落ち度のない「もらい事故」の場合、「自分は悪くないのだから、あとは保険会社がすべて対応してくれるはず」とお考えになるのは当然のことです。
しかし、実際にはご自身で対応しなければならないことが多く、今後どうなるのか、誰に相談すればよいのか、不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、交通事故の専門家である弁護士が、過失割合10対0のもらい事故に遭われた方が知っておくべき重要なポイントを、順を追って分かりやすく解説します。
誰が損害を賠償するのか、なぜご自身の保険会社への連絡が必要なのか、そして、正当な補償を受けるために何をすべきか。
皆様の不安に寄り添い、一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。
コラム作成者の紹介
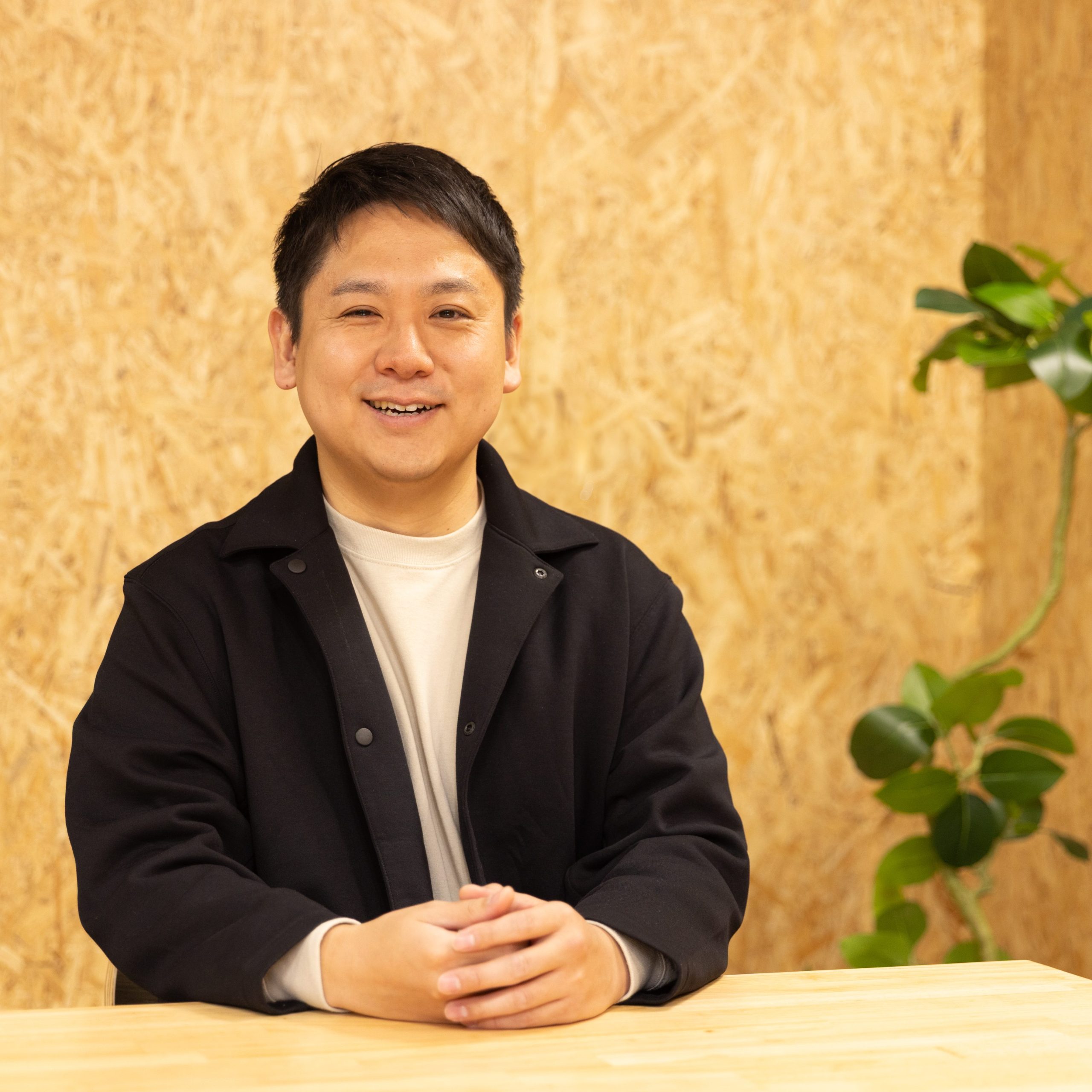
愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
事故の10対0(もらい事故)とは
交通事故における「過失割合」とは、事故が発生したことに対する各当事者の責任の度合いをパーセンテージで示したものです。
例えば、一方の責任が7割、もう一方が3割といった形で表されます。
この割合は、最終的に受け取る、あるいは支払う損害賠償の金額を決定する上で非常に重要な要素となります。
警察は事故の事実を記録しますが、過失割合の決定には介入せず、これは当事者間の民事上の問題として、主に保険会社同士の協議によって決められます。
その中で「10対0」の事故とは、一方の当事者に100%の責任があり、もう一方の当事者(被害者)には全く責任がない状態を指します。
これは一般的に「もらい事故」と呼ばれ、被害者の損害賠償額がご自身の過失によって減額される「過失相殺」が適用されないケースです。
過失割合が10対0になる典型的なケースには、以下のようなものがあります。
- 停車中に追突された事故:
- 信号待ちや渋滞で完全に停車しているところに、後方から追突された場合です。道路交通法第26条では、後続車は前方の車両が急停止しても追突を避けられる安全な車間距離を保つ義務があると定められており、この義務違反から追突した側に100%の過失が認められるのが原則です。
- センターラインをはみ出した車両との衝突事故:
- 対向車がセンターラインを越えて走行してきて、自車と正面衝突した場合。
- 赤信号を無視した車両との衝突事故:
- こちらが青信号で交差点を直進している際に、赤信号を無視して交差点に進入してきた車両に衝突された場合。
過失割合が10対0の場合、誰の保険を利用するのか
ご自身に全く非がない10対0の事故では、損害の賠償は誰が、そしてどのように行われるのでしょうか。ここには、多くの方が誤解しがちな重要なポイントが含まれています。

原則として加害者の保険を利用する
交通事故によって損害を受けた場合、その賠償責任は加害者が負うことになります。これは民法第709条の不法行為に基づく損害賠償責任として定められています。
この条文に基づき、事故によって生じた治療費や車の修理代、精神的苦痛に対する慰謝料など、すべての損害は加害者が賠償する義務を負います。
したがって、賠償金は加害者が加入している自賠責保険(強制保険)および任意保険から支払われることになります。
10対0の場合は示談代行を利用できない
多くの方が自動車保険に加入する際、万が一の時には自分の保険会社が相手方と交渉してくれる「示談代行サービス」を期待されることでしょう。
しかし、過失割合が10対0のもらい事故では、被害者はご自身が加入している保険会社の示談代行サービスを利用することができません。
この理由は、弁護士法第72条にあります。この法律は、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で、他人のために法律事務(示談交渉など)を行うこと(非弁行為)を禁止しています。
保険会社が示談代行を行えるのは、自社の契約者に過失があり、保険会社が相手方へ賠償金を支払う可能性がある、つまり自社の利害に関わる場合に限られるという例外的な扱いです。
過失が0の被害者の場合、ご自身の保険会社は相手方への支払い義務が一切生じません。
そのため、被害者の代理として交渉を行うと、この弁護士法に抵触してしまうのです。
この結果、全く落ち度のない被害者の方が、加害者側の保険会社の交渉担当者とたった一人で向き合わなければならないという、非常に不利な状況が生まれてしまいます。
過失割合10対0でも自分の保険会社に連絡すべき3つの理由
示談代行サービスが利用できないのであれば、自分の保険会社に連絡する必要はないのでしょうか。
答えは「いいえ」です。たとえ10対0の事故であっても、ご自身の保険会社への連絡は非常に重要です。
それには、主に3つの理由があります。
正確な過失割合を立証するため
事故直後は加害者が100%の非を認めていても、後になって加害者側の保険会社が「被害者にも少しは過失があったはずだ」と主張し、9対1などの過失割合を提示してくるケースは少なくありません。賠償額を少しでも減らすためです。
このような場合に備え、ご自身の保険会社に事故を報告しておけば、10対0であることを客観的に証明するためにどのような証拠(事故現場の写真、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言など)が必要か、専門的なアドバイスを受けることができます。
交渉はできなくとも、手続き面での心強い相談相手となってくれるでしょう。
契約内容や補償についての案内を受けるため
ご自身が加入している自動車保険には、示談交渉を待たずに利用できる有益な補償が含まれている可能性があります。
代表的なものが「人身傷害保険」です。
この保険は、ご自身の過失割合にかかわらず、契約で定められた上限額の範囲内で、治療費や休業損害などの実際の損害額を受け取れるものです。
加害者側との示談が長引いた場合でも、この保険を利用することですぐに治療費などを受け取ることができ、当面の経済的な不安を解消できます。
また、「車両保険」に加入していれば、それを使って先に車の修理を進めることも可能です。
その場合、ご自身の保険会社が立て替えた修理費用を、後から加害者側の保険会社に請求(求償)してくれます。
弁護士特約の利用について確認するため
10対0の事故で最も重要となるのが「弁護士費用特約」の存在です。

これは、相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が補償してくれる特約です。
一般的に、上限額は300万円程度に設定されており、ほとんどの交通事故案件ではこの範囲内で弁護士費用をまかなうことができます。
そして何より、この特約を利用しても、翌年度の保険の等級(ノンフリート等級)は下がりません。
つまり、この特約があれば、自己負担なく法律の専門家である弁護士に交渉を依頼し、前述した「被害者一人が相手方保険会社と対峙する」という不利な状況を根本から解決することができるのです。
10対0の事故で加害者の保険会社に請求できるもの
加害者に100%の過失がある場合、被害者は事故によって生じた全ての損害について賠償を請求する権利があります。
具体的には、以下のような項目が挙げられます。
治療費
事故による怪我の治療にかかった費用です。診察料、入院費、手術費用、薬代、リハビリテーション費用など、治療のために必要かつ妥当な実費全額が対象となります。
慰謝料
事故によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。これには主に3つの種類があります。
- 入通院慰謝料:
- 怪我で入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。
- 後遺障害慰謝料:
- 治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料。
- 死亡慰謝料:
- 被害者が亡くなられた場合の、ご本人およびご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。
休業損害
事故による怪我で仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合の補償です。会社員だけでなく、自営業者や主婦(主夫)の家事労働なども対象となります。
逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下したり、死亡したりしたことで、将来得られるはずだった収入が得られなくなったことに対する補償です。
車の修理代
事故で損傷した自動車の修理費用です。修理が不可能な場合(全損)や、修理費が車の時価額を上回る場合は、事故時点での車の時価額相当額が賠償されます。
なお、自賠責保険は人身損害のみを対象とするため、車の修理代などの物損は補償対象外です。
見舞金
見舞金は、法律上の損害賠償項目ではなく、加害者が謝罪の意を示すために任意で支払うものです。
そのため、加害者側の保険会社に対して法的に請求できるものではありません。
もらい事故に遭った際の対応の流れ
万が一もらい事故に遭ってしまった場合、混乱してしまうのは当然ですが、落ち着いて以下の手順で対応することが、ご自身の権利を守る上で非常に重要です。

- 負傷者の救護と危険防止
- 何よりもまず、負傷者がいれば救護活動を行います。これは道路交通法第72条で定められた運転者の義務です。また、後続車による二次被害を防ぐため、ハザードランプを点灯させ、車を安全な場所に移動させるなどの危険防止措置を講じます。
- 警察への連絡
- 怪我の有無や事故の大小にかかわらず、必ず警察(110番)に連絡してください。これも法律上の義務であり、保険金の請求に不可欠な「交通事故証明書」を発行してもらうための前提となります。
- 相手方の情報確認
- 相手方の氏名、住所、連絡先、勤務先、そして加入している自賠責保険と任意保険の会社名・証券番号などを正確に確認します。運転免許証や車検証を見せてもらい、記録しておくと確実です。
- 事故状況の記録と証拠保全
- 記憶は薄れてしまうため、スマートフォンのカメラなどで事故現場の状況を多角的に撮影しておきましょう。車両の損傷箇所、ブレーキ痕、道路状況などが分かるように記録します。ドライブレコーダーの映像は最重要の証拠となるため、必ず保存してください。目撃者がいれば、連絡先を聞いておきましょう。
- 自分の保険会社への連絡
- 事故の報告と、前述した人身傷害保険や弁護士費用特約などが利用できるかを確認するために、ご自身の保険会社にも速やかに連絡を入れます。
- 病院での受診
- 事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、後から症状が現れることは少なくありません。目立った外傷がなくても、必ず病院で診察を受けてください。事故から受診までの期間が空くと、怪我と事故との因果関係を証明することが難しくなる場合があります。
すべての運転者は、互いに配慮し、安全な交通環境を築く責任があります。愛媛県では「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」において、道路を共有する者同士の配慮を求めています。
これは自動車同士の事故においても通じる精神であり、全てのドライバーが心に留めておくべき責務です。
10対0の示談交渉をスムーズに進めるためのポイント
被害者ご自身で交渉に臨む必要がある10対0の事故。正当な賠償を受けるために、以下のポイントを心掛けてください。
必ず警察と保険会社に連絡する
警察への届出は、事故の公的な記録を残すために不可欠です。
ご自身の保険会社への連絡は、利用可能な補償や特約を確認し、いざという時のサポート体制を確保するために必須です。
この二つの連絡を怠ると、交渉のスタートラインに立つことさえ難しくなります。
事故状況の証拠を残しておく
示談交渉において、過失割合や損害の程度を証明する責任は、原則として請求する側(被害者)にあります。
「言った、言わない」の水掛け論を避け、客観的な事実で交渉を進めるために、写真や映像、第三者の証言などの証拠が極めて重要になります。
早期に病院を受診する
事故による怪我の治療はもちろんですが、適切な賠償を受けるためにも早期の受診と継続的な通院が大切です。医師の診断書や通院の記録は、怪我の程度や治療の必要性を証明する客観的な証拠となります。
治療に間が空いたり、自己判断で通院を中断したりすると、相手方保険会社から治療の打ち切りを主張される原因にもなりかねません。
一度弁護士に相談する
相手方保険会社から示談金の提示があった場合、その金額が妥当なものか、ご自身で判断するのは非常に困難です。
多くの場合、その提示額は保険会社独自の低い基準で計算されています。示談書に署名する前に、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士費用特約があれば、費用を気にすることなく専門家の助言を求めることができます。
10対0の事故でよくある質問
ここでは、もらい事故に遭われた方からよく寄せられる質問にお答えします。
過失割合10対0の場合の示談金相場は?
「相場はいくら」と一概に言うことはできません。
示談金の額は、怪我の程度、治療期間、後遺障害の有無、休業の状況、年齢、収入など、個別の事情によって大きく変動するためです。
重要なのは、示談金の計算には3つの異なる基準が存在するという点です。
- 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償基準。
- 任意保険基準:各保険会社が独自に用いる非公開の基準。
- 裁判所・弁護士基準:過去の裁判例に基づく、法的に最も正当とされる基準。
相手方保険会社が提示してくるのは「任意保険基準」ですが、弁護士が介入することで最も高額な「裁判所・弁護士基準」での交渉が可能となり、最終的な受取額が大きく変わることがあります。
10対0の場合、車の等級はどうなる?
相手方からの賠償金のみで車の修理代などをまかない、ご自身の車両保険を利用しなかった場合、保険の等級(ノンフリート等級)は下がりません。
ただし、修理を急ぐなどの理由でご自身の車両保険を先行して利用した場合、保険契約の内容によっては「1等級ダウン事故」として扱われ、翌年の等級が1つ下がり、保険料が上がってしまう可能性があります。
慰謝料を増額する方法はある?
慰謝料を増額するための最も有効な方法は、弁護士に交渉を依頼することです。
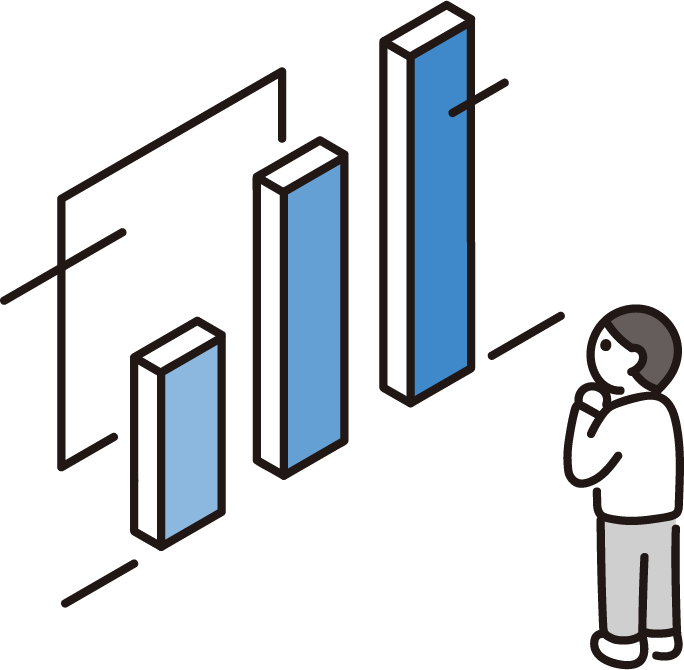
前述の通り、慰謝料の算定基準には3つのレベルがあり、どの基準を用いるかで金額が大きく異なります。
| 基準 | 概要 | 金額水準 |
| 自賠責基準 | 法律で定められた、被害者救済のための最低限の補償。 | 最も低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している非公開の基準。自賠責基準よりは高いが、十分とは言えないことが多い。 | 中程度 |
| 弁護士・裁判所基準 | 過去の裁判例を基に作られた基準。弁護士が交渉や裁判で用いるもので、法的に最も正当な水準。 | 最も高い |
相手方保険会社は、自社の支払いを抑えるため、当然ながら自社の「任意保険基準」で計算した低い金額を提示してきます。
弁護士は、最も高い「弁護士・裁判所基準」を根拠に交渉を行うため、慰謝料を含む賠償金全体が大幅に増額される可能性が高まります。
まとめ
ご自身に全く非のない10対0のもらい事故であっても、残念ながら受け身の姿勢でいては、正当な補償を受けられない可能性があります。
- ご自身の保険会社は、弁護士法の規定により、示談交渉を代行してくれません。
- 被害者ご自身が、交渉のプロである相手方保険会社の担当者と直接やり取りをする必要があります。
- 相手方保険会社の提示額は、法的に正当な基準よりも低い水準で計算されていることがほとんどです。
しかし、ご自身が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、費用の心配なく弁護士に交渉を依頼することができます。
これは、もらい事故の被害に遭われた方が、ご自身の権利を守るための非常に強力な武器となります。
突然の事故で心身ともにお辛い中、複雑な交渉までご自身で抱え込む必要はありません。
専門家の力を借りることで、精神的な負担を軽減し、治療に専念しながら、適正な賠償の実現を目指すことができます。
交通事故に遭い、今後の対応にご不安を感じていらっしゃる方は、どうぞお一人で悩まず、nac刑事法律事務所にご相談ください。
専門家があなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案します。

