2025年7月8日
検察庁の呼び出しはどんな理由?期間や回数・ポイントを解説
ある日突然、検察庁から電話や手紙で呼び出しを受けたら、誰でも不安になるものです。「これからどうなってしまうのだろう」「何か大変なことになるのではないか」と、一人で悩んでいませんか?
検察庁からの呼び出しは、多くの場合、警察での捜査が終わり、事件が次の段階に進んだことを意味します。
しかし、呼び出されたからといって、必ずしも厳しい処分が待っているわけではありません。
この記事では、法律に精通した専門家の視点から、検察庁から呼び出される理由、手続きの流れ、そして呼び出しに際して知っておくべき重要なポイントを、ご不安な気持ちに寄り添いながら、分かりやすく解説します。
今後の見通しを立て、適切に行動するための一助となれば幸いです。
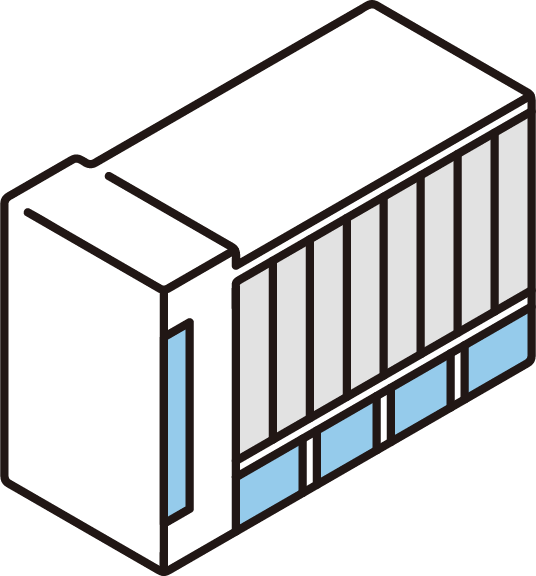
コラム作成者の紹介
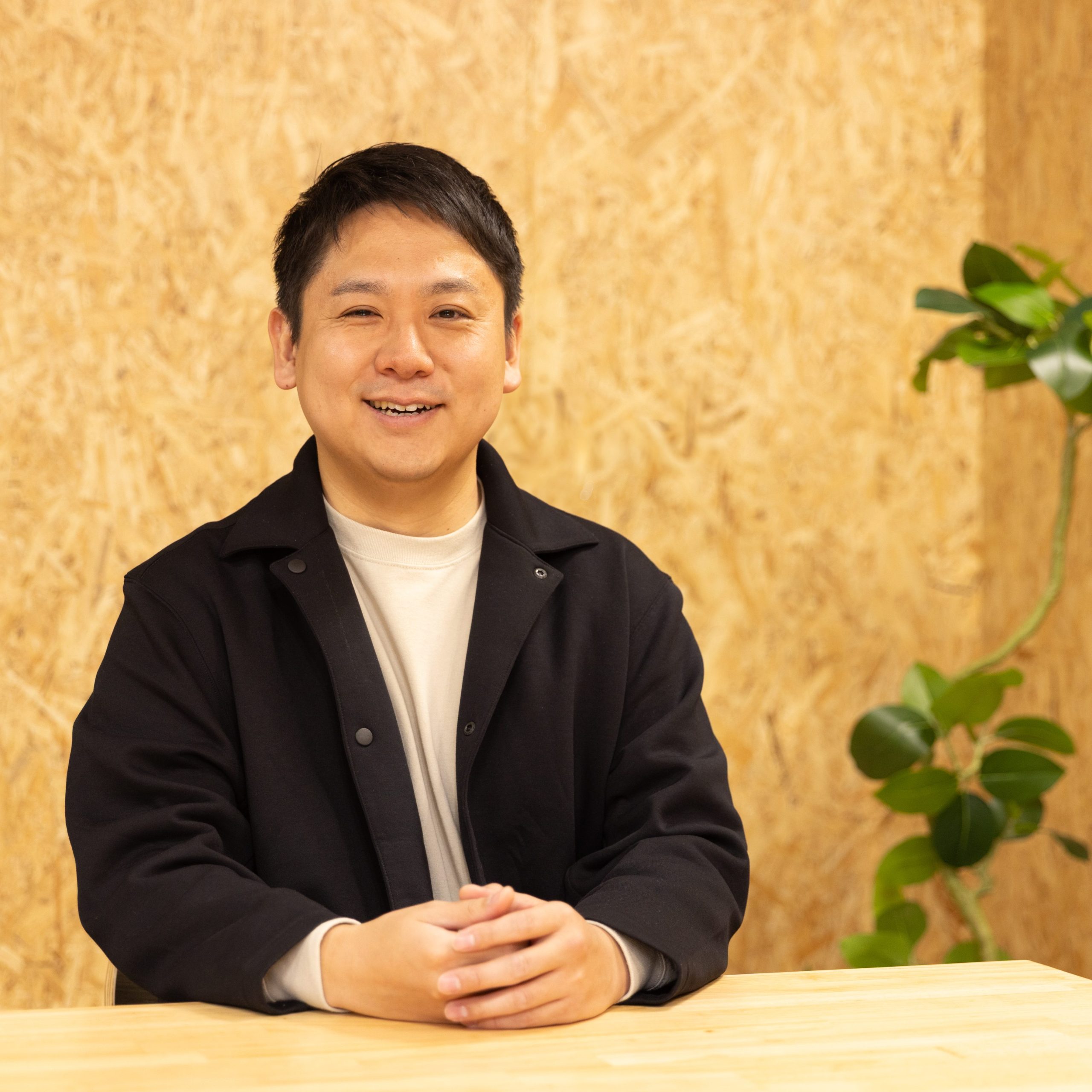
愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
実際に松山地方検察庁へ出頭する方は、具体的で実践的な情報をまとめた次のコラムもご覧ください。
1. 検察庁から呼び出される理由
警察による捜査が終わると、事件は検察庁に送られます(「送致」といいます)。
検察官は、警察から引き継いだ捜査資料を精査し、事件を裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を最終的に判断する権限を持っています。
検察庁からの呼び出しは、この最終判断のための手続きの一環であり、主に以下の4つの理由が考えられます。
1-1. 取り調べを受けるため
検察官が、起訴・不起訴の判断を下すために、ご本人から直接話を聞く必要がある場合です。
警察での取り調べと重複する内容を質問されることもありますが、その目的は異なります。
警察の捜査が主に犯人を特定し証拠を集めることにあるのに対し、検察官の取り調べは、警察の捜査内容に誤りがないか、法的な観点から事件を精査し、起訴して有罪を立証できるかを判断するための「補充捜査」という位置づけです。
検察官は、捜査の最終責任者として、中立的な立場で事件全体を見直し、被疑者の言い分にも耳を傾けます。
したがって、この取り調べは、ご自身の状況や考えを最終判断権者である検察官に直接伝えることができる、非常に重要な機会となります。
1-2. 起訴・不起訴の判断を受けるため
検察官が取り調べを終え、事件に対する最終的な処分を決定した際に、その内容を本人に告知するために呼び出すことがあります。
特に、事実関係に争いのない事件では、最後の取り調べと同じ日に処分が言い渡されることも少なくありません。
処分には、裁判にかける「起訴」と、裁判にかけずに事件を終了させる「不起訴」があります。
不起訴処分の中には、犯罪の証拠は十分にあるものの、被害者との示談が成立している、本人が深く反省している、といった様々な事情を考慮して検察官の裁量で起訴を見送る「起訴猶予」という処分もあります。
1-3. 略式起訴を受けるため
比較的軽微な事件(例えば、100万円以下の罰金または科料に相当する事件)について、検察官が公開の法廷での裁判ではなく、書面審理だけで罰金刑を求める「略式手続(略式起訴)」を検討している場合があります。
この手続きは、被疑者本人の同意がなければ進めることができません。
そのため、検察官が本人を呼び出し、略式手続の内容を説明し、同意するかどうかの意思を確認します。
同意すれば、裁判所に行くことなく罰金額が決定されますが、罰金刑であっても「前科」がつくことになりますので、慎重な判断が必要です。

1-4. 参考人として呼び出したいため
検察庁からの呼び出しは、必ずしも事件の当事者(被疑者)としてだけではありません。
事件に関する何らかの情報を持っていると思われる場合、「参考人」として話を聞くために呼び出されることがあります。
参考人とは、法律上「被疑者以外の者」を指し、事件の目撃者や、被疑者の知人・家族などが該当します。刑事訴訟法は、捜査機関が必要な場合には被疑者以外の者も取り調べることができると定めています。
刑事訴訟法第223条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
参考人としての呼び出しは任意であり、応じる義務はありません。
しかし、捜査への協力を拒んでいると受け取られる可能性もあるため、基本的には応じるのが賢明です。ご自身がどの立場で呼ばれているのかを理解することは、今後の対応を考える上で非常に重要です。
| 立場 | 定義 | 逮捕の可能性 | 黙秘権の告知 |
| 被疑者 | 犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者。 | あり | 義務あり(刑事訴訟法第198条第2項) |
| 重要参考人 | 法律上の用語ではないが、参考人の中でも特に被疑者になる可能性が高いと考えられる者。 | 可能性あり | 義務なし |
| 参考人 | 被疑者以外で、事件に関する情報を持っている可能性がある者。 | 原則なし | 義務なし(刑事訴訟法第223条第2項) |
2. 警察の呼び出しとの違い
警察と検察は、どちらも犯罪捜査を行う機関ですが、その役割と権限には明確な違いがあります。
この違いを理解することが、検察からの呼び出しの重みを正しく認識することにつながります。
警察の取り調べは、主に犯罪事実を明らかにし、証拠を収集し、犯人を特定するための第一次的な捜査です。
一方、検察官の取り調べは、警察から送られてきた事件を法的な観点から再検討し、被疑者を刑事裁判にかけるべきか(起訴するか)を最終的に決定するための、いわば「仕上げの捜査」です。
最も大きな違いは、起訴する権限は検察官だけが持っているという点です(起訴独占主義)。警察官は、どれだけ捜査を尽くしても、自ら事件を起訴することはできません。
検察官は、警察の捜査結果を鵜呑みにするのではなく、独自の視点で証拠を評価し、被疑者の言い分も聞いた上で、社会正義の観点から起訴・不起訴を判断する重い責任を負っています。
3. 検察庁から呼び出される方法
検察庁からの呼び出しは、主に「電話」または「手紙」で行われます。
どちらの方法も正規の手続きであり、慌てず冷静に対応することが大切です。
3-1. 電話
担当の検察官や検察事務官から直接電話がかかってくるケースです。
突然のことで動揺するかもしれませんが、まずは落ち着いて、担当者の氏名、所属部署、連絡先、そして指定された出頭日時と場所を正確にメモに取りましょう。
聞き取れなかった場合は、遠慮なく聞き返して問題ありません。

3-2. 手紙
「呼出状」と書かれた手紙が自宅に郵送で届くこともあります。
この書面には、出頭すべき検察庁の場所、日時、担当検察官名、持ち物などが記載されています。
手紙はなくさないよう大切に保管し、記載されている連絡先に問い合わせれば、日程の調整などについて相談することも可能です。
4. 呼び出しがあるまでの期間や回数
警察での取り調べが終わってから、「次は検察庁から連絡があります」と言われたものの、なかなか連絡が来ないと、かえって不安が増すかもしれません。
呼び出しまでの期間や回数には、ある程度の傾向はありますが、事件によって大きく異なります。
呼び出しまでの期間
警察から検察庁へ事件が送られてから、実際に呼び出しがあるまでの期間に決まりはありません。
早い場合は1ヶ月程度ですが、一般的には数ヶ月かかることも珍しくありません。
事件が複雑であったり、検察官が多忙であったりすると、半年以上かかるケースもあります。
連絡がないからといって、すぐに「忘れられたのではないか」と考える必要はありません。
呼び出しの回数
呼び出しの回数も法律で定められているわけではありません。
事実関係を認めている比較的簡単な事件であれば、1回か2回の取り調べで終了することがほとんどです。
一方で、容疑を否認している場合や、被害者・目撃者の証言と食い違いがある場合などは、検察官が入念に事実確認を行うため、複数回にわたって呼び出される可能性があります。
5. 検察庁から呼び出しがこない理由
警察での捜査が終わってから何ヶ月も連絡がないと、「どうなっているのだろう」と不安な日々を過ごすことになります。
しかし、連絡がないことには、いくつかの理由が考えられます。
5-1. 証拠収集など捜査に時間がかかっている
検察官が、警察から送られてきた証拠だけでは不十分だと判断し、追加の証拠収集や関係者への聞き込みなど、さらなる捜査を行っている可能性があります。
特に、容疑を否認している事件では、検察官は有罪を立証するために慎重に裏付け捜査を進めるため、時間がかかる傾向にあります。
また、逮捕・勾留されていない在宅事件の場合、身柄事件のような厳格な時間制限がないため、捜査が長期化することもあります。
5-2. 不起訴処分になった
連絡がない最も良い理由として、すでに「不起訴処分」となり、事件が終了しているケースが考えられます。
起訴された場合は、裁判所から「起訴状」という書類が自宅に届くため、必ず知ることができます。
しかし、不起訴になった場合、検察官にはその事実を被疑者に通知する法的な義務はありません。
そのため、ご自身が知らない間に事件が終わっているということもあり得るのです。
ただし、不起訴になった場合、被疑者はその証明書の発行を請求する権利が法律で保障されています。
刑事訴訟法第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
この「不起訴処分告知書」を請求することで、事件が正式に終了したことを確認できます。
5-3. 別の事件で検察官が忙しい
検察官が連絡をしないのは、個人的な理由ではなく、単に多忙であるという制度的な問題も大きな要因です。
法務省の「令和5年版 犯罪白書」によると、令和4年に全国の検察庁が新たに受理した事件の総数は約74万人にのぼります。
一人の検察官は常に複数の事件を抱えており、特に容疑者が逮捕・勾留されている「身柄事件」は、法律上の時間制限が厳しいため、優先的に処理しなければなりません。
そのため、ご自身の事件が身柄拘束されていない「在宅事件」である場合、他の緊急性の高い事件の処理のために、手続きが後回しになることは日常的に起こり得ます。
6. 検察庁に呼び出された時のポイント
実際に検察庁へ出頭する日、ご不安は頂点に達するかもしれません。
しかし、事前にポイントを押さえて準備しておくことで、冷静に対応し、不利益を最小限に抑えることができます。

6-1. 弁護士にすぐ相談する
最も重要なポイントは、検察庁からの呼び出しに応じる「前」に、できるだけ早く弁護士に相談することです。
検察官の取り調べは、起訴・不起訴を決める最終段階であり、一度取り調べが終わると、その直後に処分が決定されてしまうことが少なくありません。
うなると、後から弁護士が介入しても、決定を覆すことは極めて困難になります。
弁護士に事前に相談すれば、
- 事件の内容に応じた取り調べへの対応方法(何を話し、何を話すべきでないか)について具体的なアドバイスを受けられる。
- 被害者がいる事件であれば、検察官に事情を説明して時間をもらい、示談交渉を進めることができる可能性がある。
- 不起訴処分を目指すための最善の弁護活動を、最も効果的なタイミングで開始できる。
といったメリットがあります。呼び出しを受けてからでは手遅れになる前に、まずは専門家である弁護士に相談することが、ご自身を守るための最善策です。
6-2. 持ち物は身分証明書と印鑑は用意する
出頭の際には、持ち物を確認しておくと安心です。
一般的に必要とされるのは以下のものです。
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印で構いません)
- 呼び出し状(手紙で呼び出された場合)
印鑑は、取り調べの内容を記録した「供述調書」に署名・押印するためや、略式起訴に同意する場合の同意書に使用されることがあります。
ただし、印鑑の持参を求められたからといって、必ず起訴されるわけではないので、過度に心配する必要はありません。
6-3. 服装はスーツでなくても問題ない
服装に決まりはありませんが、検察官に与える印象を考慮し、清潔感のある落ち着いた服装を心がけるのが無難です。
必ずしもスーツである必要はありませんが、ジャージや派手な服装など、あまりにだらしない格好は避けるべきでしょう。
襟付きのシャツやジャケットなど、誠実な印象を与える服装が望ましいです。
6-4. サインは慎重にする
取り調べの最後に、話した内容をまとめた「供述調書」への署名・押印を求められます。
この供述調書は、一度署名・押印してしまうと、後の裁判で極めて強力な証拠となります。そのため、安易にサインしてはいけません。

法律では、署名・押印の前に、調書の内容を閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないか確認する機会を与えることが義務付けられています。
刑事訴訟法第198条第4項
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
もし、ご自身の話した内容と少しでも違う点や、ニュアンスが異なると感じる部分があれば、遠慮なく訂正を求めなければなりません。
そして、内容に納得できない場合は、署名・押印を拒否する権利があります。
刑事訴訟法第198条第5項但書
(被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。)但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
「早く帰りたい」という気持ちから内容をよく確認せずにサインしてしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。
6-5. 黙秘権を行使するかは弁護士と相談する
憲法および刑事訴訟法は、誰であっても自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち「黙秘権」を保障しています。
取り調べの冒頭で、検察官からこの権利について説明があるはずです。
刑事訴訟法第198条第2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
答えたくない質問に対しては、黙っていることができます。
しかし、黙秘権の行使は、時として「反省していない」という印象を与えかねないなど、非常に高度な判断を要する戦術です。
どの部分で黙秘し、どの部分で積極的に話すかという戦略は、事件の状況によって全く異なります。
したがって、黙秘権を行使するかどうか、どのように行使するかは、必ず事前に弁護士と相談して決めるべきです。
7. 元検事の弁護士に相談するメリット
検察庁からの呼び出しという困難な状況において、弁護士は心強い味方となります。
特に、検察官としての実務経験を持つ「元検事の弁護士」に相談することには、他にはない大きなメリットがあります。
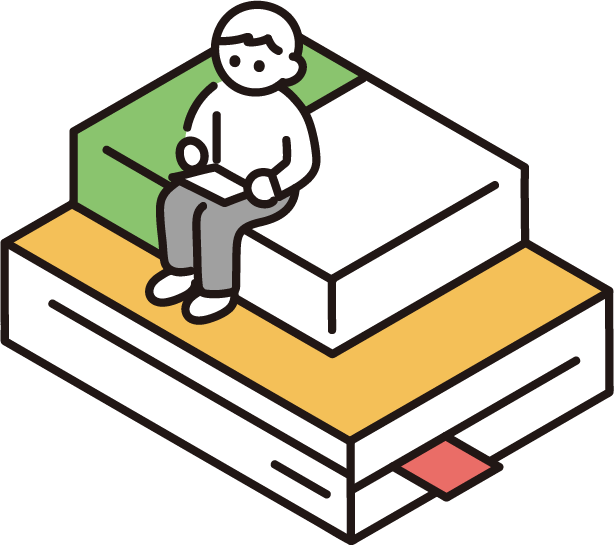
7-1. 検察官の視点を踏まえた的確な助言が期待できる
元検事の弁護士は、かつて検察官として数多くの事件を処理した経験から、検察官がどのような証拠を重視し、被疑者のどのような点を問題視するのか、その思考回路を深く理解しています。
そのため、取り調べで何が聞かれ、どのように答えれば有利な状況を導きやすいか、あるいは不利な状況を避けられるかについて、極めて具体的かつ戦略的なアドバイスを提供できます。
事前に元検事の弁護士と綿密な打ち合わせを行うことで、検察官の質問の意図を先読みし、落ち着いて取り調べに臨むことが可能になります。
7-2. 不起訴に向けた効果的な示談交渉ができる
痴漢や盗撮(愛媛県迷惑行為防止条例違反など)、暴行、窃盗といった被害者がいる事件では、「示談」の成立が不起訴処分を獲得する上で極めて重要な要素となります。
しかし、ただ示談をすれば良いというわけではありません。
元検事の弁護士は、どのような内容の示談であれば、検察官が「被害者の被害感情は十分に慰謝され、処罰の必要性は低い」と判断しやすいかを、実務経験に基づいて熟知しています。被害者の感情に配慮しつつ、検察官の判断のポイントを押さえた示談交渉を進めることで、不起訴処分の可能性を最大限に高めることができます。
加害者本人が交渉することが難しいケースでも、元検事という肩書が被害者の信頼を得やすくし、円滑な交渉につながることも期待できます。
8. 検察庁の呼び出しにおけるよくある質問
最後に、検察庁からの呼び出しに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
8-1. 呼び出しは無視したらいけない?
被疑者としての呼び出しは、法律上は「任意」であり、強制力はありません。
しかし、正当な理由なく無視し続けることは絶対に避けるべきです。
呼び出しに応じない態度は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断される原因となり、かえって逮捕状を請求されるリスクを高めてしまいます。
捜査に協力的である姿勢を示すことが、ご自身の不利益を避ける上で重要です。
8-2. 呼び出し日に行けない場合はどうすればよい?
仕事の都合や体調不良など、やむを得ない事情で指定された日に出頭できない場合は、正直にその理由を伝えれば、日程を変更してもらえることがほとんどです。
大切なのは、無断で欠席するのではなく、必ず事前に担当の検察官に電話で連絡し、相談することです。
8-3. 家族が呼び出される理由はなに?
ご家族が検察庁に呼ばれる場合、いくつかの理由が考えられます。
一つは、被疑者の今後の監督者となる「身元引受人」として、協力が得られるかを確認するためです。
家族のサポート体制がしっかりしていることは、再犯防止につながるとして、検察官が処分を判断する上で有利な事情となることがあります。
また、事件に関する事情を知っている参考人として、話を聞くために呼ばれることもあります。
9. 検察庁からの呼び出しでお悩みなら、nac刑事法律事務所にご相談ください

検察庁から呼び出しを受け、今後の手続きやご自身の処分について、大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
検察官からの取り調べは、今後の刑事手続きにおいて非常に重要な意味を持ちます。
不用意な発言をしてしまい、ご自身にとって不利な状況を招いてしまうケースも少なくありません。
少しでもご不安があれば、一人で悩まず、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。
全国どこにお住まいの方からのご相談にも対応しておりますので、今後の見通しや、取り調べにどう対応すべきか、具体的なアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
【コラムをご覧になった方へ】
LINEまたはお問い合わせフォームからお問い合わせの際に「コラムを見た」とお伝えいただきますと、通常30分5,500円の初回相談を、60分5,500円でご案内いたします。
検察庁に呼び出された段階では、ご不安な点や確認したいことが多く、お話が長くなる傾向があります。
時間を気にせずお話しいただけるよう設けた特典ですので、ぜひご活用ください。
※お電話でのお問い合わせは電話代行サービスにて承っております。
そのため、お電話口で本特典についてお申し出いただいても対応いたしかねます。
また、特典の詳細についてお電話でお尋ねいただいてもお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
大変恐れ入りますが、特典をご利用の際は、必ずLINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※ご相談内容が当事務所のサポート範囲外である場合や、弁護士の都合によりご相談をお受けできないこともございます。
あらかじめご了承ください。
もし起訴されてしまったら
検察官は、取り調べの結果などを基に、あなたを起訴するかどうかを判断します。
検察庁に呼ばれているということは、起訴される可能性も否定できません。
日本の刑事裁判では、一度起訴されると99.9%が有罪になると言われており、前科がついてしまう可能性が極めて高くなります。
起訴された後の流れや、裁判で有利な判決を得るために弁護士ができることについては、以下のページで詳しく解説しています。
また、逮捕・勾留されずに在宅のまま捜査が進み、起訴される「在宅起訴」というケースもあります。
身柄拘束されていなくても、決して安心はできません。
在宅起訴については、こちらのコラムで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
不起訴処分を獲得するため、あるいは、もし起訴されても刑を軽くするためには、早期に弁護士へ相談し、適切な対応をとることが大切です。

