2025年10月7日
保釈申請は即日通る?要件や流れ・費用・通らないときの対応を解説
ご家族が逮捕され、今後のことがわからず、不安な日々をお過ごしのことと存じます。
身体拘束が続くと、ご本人はもちろん、ご家族の心身にも大きな負担がかかります。
特に、起訴された後も勾留が続く場合、「一日でも早く、元の生活に戻してあげたい」と願うのは当然のことです。
そのための重要な手続きが「保釈申請」です。
しかし、保釈という言葉は耳にしたことがあっても、具体的な内容や流れ、必要な準備については、なかなかわかりにくいものです。
このコラムでは、保釈申請に関する皆様の疑問や不安に寄り添いながら、その全体像を一つひとつ丁寧に解説していきます。
どのような制度で、何が必要なのか、そしてどのような流れで進むのかを正しく理解することで、少しでも心の負担を軽くし、次の一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。
コラム作成者の紹介
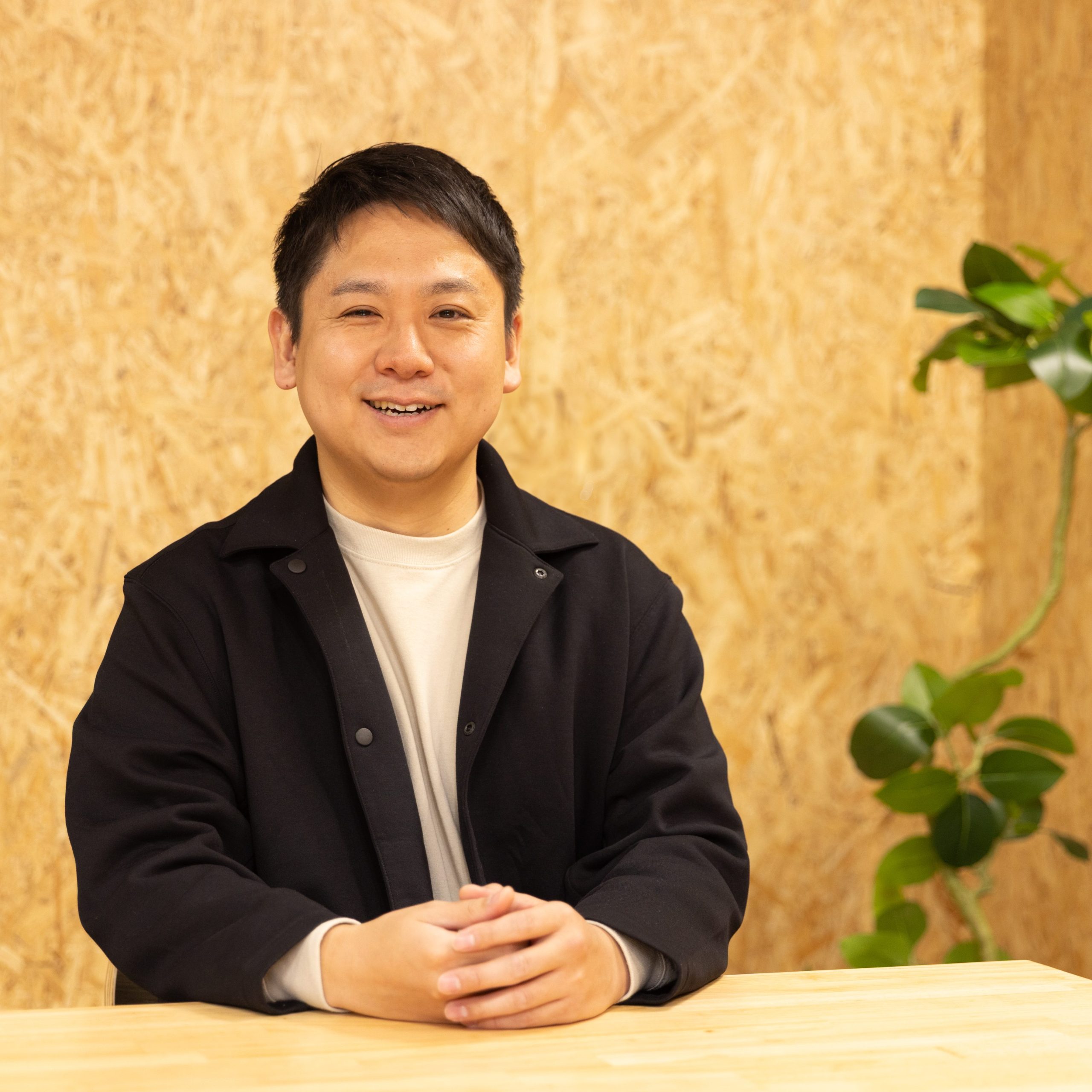
愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
保釈申請とは?
まず、保釈申請という手続きの基本的な意味合いからご説明します。
刑事手続きの中で「保釈」がどのような位置づけにあるのかを理解することは、今後の見通しを立てる上で非常に重要です。
このセクションでは、保釈の法的な定義や種類、そしてその目的について解説します。
保釈の法的意味とは?
保釈とは、起訴された後も身体拘束(勾留)が続いている被告人について、保釈保証金を裁判所に納めることを条件に、一時的にその身柄を解放する制度のことです。
ここで非常に重要なのは、「保釈」と「釈放」の違いです。
この二つの言葉は混同されがちですが、法的な意味は明確に異なります。
- 釈放:
- 逮捕や勾留といった、身体拘束されている状態から解放されること全般を指す広い言葉です。例えば、逮捕されたものの検察官が起訴しない(不起訴処分)と判断した場合や、勾留請求が裁判官に認められなかった場合に身柄が解放されるのは「釈放」です。
- 保釈:
- 「釈放」の一種ではありますが、検察官によって起訴された後に、裁判所の許可を得て、保証金を納付することで身柄が解放される手続きを指します。
つまり、逮捕されてから起訴されるまでの間(最長23日間)は、原則として保釈を申請することはできません。
ご家族が逮捕されてすぐに「保釈してほしい」と思われても、法的には「起訴」という段階を経なければ、保釈申請のスタートラインに立てないのです。
この違いを理解しておくことは、ご家族の精神的な負担を軽減し、現実的な見通しを立てる上で不可欠です。
保釈には3つの種類がある
保釈は、刑事訴訟法という法律に基づいており、主に3つの種類に分けられます。
裁判所は、保釈の請求があった場合、まず「権利保釈」に該当するかを判断し、該当しない場合に「裁量保釈」を検討するという流れで審査を進めます。
- 権利保釈(必要的保釈)
- これは保釈の原則となる形態です。法律で定められた特定の除外事由に当てはまらない限り、裁判所は請求を許可しなければならないとされています。被告人の権利としての側面が強いことから「権利保釈」と呼ばれます。根拠となる刑事訴訟法第89条では、以下のような除外事由が定められています。刑事訴訟法第89条保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
- 裁量保釈
- 権利保釈の除外事由に該当してしまった場合でも、諦める必要はありません。裁判所が「適当と認めるとき」は、その裁量によって保釈を許可することができます。これを裁量保釈といいます。実務上、特に罪を認めていない否認事件などでは、「罪証隠滅のおそれがある」として権利保釈が認められないケースが多く、この裁量保釈を得られるかどうかが極めて重要になります。刑事訴訟法第90条には、裁判所が考慮すべき事情が示されています。刑事訴訟法第90条裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。弁護士は、これらの事情を具体的に主張し、裁判官に保釈を認めてもらうよう働きかけます。
- 義務的保釈
- 勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が保釈を許可しなければならないとするものです。刑事訴訟法第91条に定めがありますが、実務上、この規定によって保釈が認められることはほとんどありません。
保釈申請は勾留から一時開放してもらうために行う手続き
保釈申請の目的は、判決が確定するまでの間、被告人を一時的に身体拘束から解放することにあります。
日本の刑事裁判では「無罪推定の原則」があり、有罪判決が確定するまでは、誰もが罪を犯していない者として扱われなければなりません。
しかし、起訴後に勾留が続くと、裁判が終わるまで数ヶ月、時には年単位で社会から隔離されてしまいます。
その結果、職を失ったり、家族関係に深刻な影響が出たりと、計り知れない不利益を被る可能性があります。
保釈は、こうした過大な不利益を避け、被告人が家族のもとで生活しながら、弁護士と十分に裁判の準備を進めることを可能にするための、非常に重要な手続きなのです。

保釈申請は即日で通る?目安の日数を紹介
ご家族にとって最も気になる点の一つが、「保釈申請をしたら、いつ身柄が解放されるのか」ということでしょう。
結論から申し上げますと、申請したその日のうちに保釈が認められる「即日保釈」は、極めて稀なケースです。
一般的に、弁護士が裁判所に保釈請求書を提出してから、裁判官が許可または却下の決定を下すまでに、2~3営業日ほどかかります。
裁判所は土日祝日には保釈の審査を行わないため、例えば金曜日に申請した場合、決定が出るのは早くても週明けの月曜日か火曜日になります。
さらに、裁判官から保釈許可決定が出た後、指定された保釈保証金を裁判所に納付し、その確認が取れてから、実際に留置施設に釈放の連絡が入ります。
この手続きにも数時間を要するため、許可決定が出た日の夕方以降に釈放されるのが一般的です。
このタイムラインは、あくまで手続き上のものです。
しかし、経験豊富な弁護士は、起訴されることを見越して、事前に保釈請求書や身元引受人の書面などの準備を周到に進めます。
そして、検察官が起訴したその瞬間に、間髪入れずに裁判所へ申請を行うことができます。
このように、手続きの開始を1分1秒でも早めることが、結果として数日間の身体拘束期間の短縮につながるのです。
この迅速な対応こそが、弁護士に依頼する大きな意義の一つと言えるでしょう。
申請するための要件3つ
保釈を勝ち取るためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
これらは法律上の形式的な条件だけでなく、裁判官に「この人を保釈しても問題ない」と判断してもらうための実質的な条件も含まれます。
ここでは、その中でも特に重要な3つの要件について解説します。
起訴されているが重罪でない
保釈申請の前提として、被告人が起訴されていることが必要です。
そして、権利保釈が認められるためには、先述した刑事訴訟法第89条の除外事由に該当しないことが求められます。
具体的には、殺人や強盗致傷など、法定刑が「短期1年以上の懲役・禁錮」にあたるような重大犯罪ではないこと、過去に重大犯罪で有罪判決を受けた経歴がないことなどが挙げられます。
そして、実務上最も大きな壁となるのが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」という除外事由です。
罪を認めていない場合や、共犯者がいる事件などでは、検察官がこの点を強く主張し、保釈に反対することが多くあります。
このような状況で保釈を実現するためには、弁護士が「罪証隠滅の具体的なおそれはない」ということを、説得力をもって裁判官に主張する必要があります。
身元保証人を準備できる
法律の条文に明記されているわけではありませんが、保釈を実現するためには、身元引受人の存在が事実上不可欠です。
身元引受人とは、保釈された被告人の生活を監督し、裁判に必ず出廷させることを裁判所に対して約束する人のことです。
通常、ご両親や配偶者など、同居するご家族が身元引受人になることがほとんどです。
裁判官は、被告人が保釈中に逃亡したり、被害者や証人に接触したりしないかを懸念しています。
信頼できる身元引受人が監督役となることで、そうした懸念が払拭され、保釈が許可されやすくなるのです。
弁護士は、身元引受人の方に「身元引受書」という書類を作成していただき、保釈請求書と共に裁判所に提出します。
保釈保証金を用意できる
保釈が許可される際には、必ず保釈保証金の金額が定められます。
これは罰金とは異なり、被告人が逃亡したりせず、裁判にきちんと出廷することを担保するためのお金です。
いわば、裁判所への「預け金」のようなものです。
したがって、保釈中の条件をすべて守り、裁判が終了すれば、判決内容にかかわらず(たとえ有罪判決であっても)納付した保証金は全額返還されます。
この点は、ご家族にとって非常に重要なポイントですので、ぜひ覚えておいてください。
保釈許可の決定が出ても、この保証金を納付しない限り、被告人が釈放されることはありません。
刑事訴訟法第94条は、保証金の納付があって初めて保釈の決定を執行できると定めています。
保釈までの流れと申請のやり方
ここからは、実際に逮捕されてから保釈が認められるまでの具体的な流れと、申請手続きの詳細について解説します。
複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを理解することで、全体像が見えてくるはずです。
申請ができるまでの流れ
保釈申請は、刑事手続きのある特定の段階に至らなければ行うことができません。
その前提となる流れを簡潔に見ていきましょう。
- 逮捕:警察に身柄を拘束されます。この期間は最長で72時間です。
- 勾留: 逮捕に続き、検察官が「さらに捜査のために身柄拘束が必要」と判断し、裁判官に請求して許可されると、原則10日間、延長されるとさらに10日間、合計で最長20日間の身体拘束が続きます。
- 起訴: 勾留期間が満了するまでに、検察官が事件を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を決定します。この「起訴」の決定がなされた時点から、初めて保釈の申請が可能になります。
保釈申請の手続き一覧
起訴された後、保釈を申請してから実際に身柄が解放されるまでには、いくつかの手続きを経る必要があります。
以下で、その各ステップを詳しく解説していきます。
| ステップ | 主な手続き | 担当者・決定者 | 目安期間 |
| 1 | 保釈請求書の提出 | 弁護士 | 起訴後、即日 |
| 2 | 裁判官による審理 | 裁判官、検察官、弁護士 | 申請後1~2日 |
| 3 | 保釈許可・却下の決定 | 裁判官 | 審理後、即日~1日 |
| 4 | 保釈保証金の納付 | 弁護士、家族 | 許可決定後、即日 |
| 5 | 釈放 | 警察署・拘置所 | 納付後、数時間 |
保釈申請書を提出
保釈を求めるための最初のステップは、管轄の裁判所に対して「保釈請求書」という書面を提出することです。
この請求は、被告人本人やご家族も行うことができますが、法的な主張を的確に記載する必要があるため、実際には弁護士が行うのが通常です。
保釈請求書には、事件の内容や被告人の情報に加え、なぜ保釈が認められるべきかの理由を具体的に記述します。
さらに、先述した「身元引受書」や、被告人の反省の情を示す「上申書」、被害者との示談が成立している場合は「示談書の写し」など、保釈を認めてもらうために有利となる様々な資料を添付します。
これらの書類をいかに説得力のある形で準備するかが、弁護士の腕の見せ所となります。

検察官の意見聴取及び弁護士面接
保釈請求書が提出されると、裁判官は必ず担当の検察官に意見を求めます。
検察官は、その請求に対して「相当(保釈を認めてよい)」「不相当(保釈は認めるべきでない)」「しかるべく(裁判官の判断に任せる)」のいずれかの意見を回答します。
多くの場合、検察官は保釈に反対する「不相当」の意見を出してきます。
ここで重要になるのが、弁護士による裁判官面接です。
これは、弁護士が直接裁判官と会い、書面だけでは伝わらない被告人の人柄や、ご家族の監督体制がしっかりしていること、逃亡や証拠隠滅の恐れが具体的にないことなどを口頭で説明し、保釈の必要性を訴える機会です。
この面接は、裁判官の心証を形成する上で非常に大きな影響を与えることがあり、保釈を勝ち取るための極めて重要な活動と言えます。
裁判官による保釈許可決定
弁護士が提出した書面、検察官の意見、そして弁護士との面接内容などを総合的に考慮し、最終的に裁判官が保釈を許可するか、それとも却下するかを決定します。
許可する場合には、「保釈許可決定」が出され、そこに納付すべき保釈保証金の金額や、保釈中に守るべき条件(住居の制限など)が明記されます。
この決定は、通常、申請から2~3日後の午後に出されることが多いです。
保釈金の納付
保釈許可決定が出ても、それだけでは釈放されません。
決定書に記載された金額の保釈保証金を、裁判所の会計窓口に現金で納付する必要があります。
この納付手続きが完了して初めて、被告人の身柄を解放する手続きが進められます。
これは刑事訴訟法第94条で定められた厳格なルールです。
通常、弁護士は許可決定が出ることを見越して、ご家族に事前に保釈金の準備をお願いしておきます。
そして、決定が出たら速やかに弁護士が納付手続きを代行します。
保釈が認められる
裁判所が保釈保証金の納付を確認すると、被告人が勾留されている警察署や拘置所に対して「釈放指揮書」という書類が送られ、釈放の指示が出されます。
この連絡を受けて、留置施設では釈放に向けた事務手続きが行われ、通常、納付から2~3時間後には被告人が施設の玄関から出てくることになります。
ご本人の荷物が多い場合もあるため、ご家族がお迎えに行かれると安心です。
保釈に必要な費用はどのくらい?
保釈を実現するためには、大きく分けて2種類の費用が必要になります。
一つは裁判所に預ける「保釈保証金」、もう一つは弁護士に支払う「弁護士費用」です。
保釈保証金の金額は、事件の重大さや被告人の経済力などを考慮して裁判官が決定します。
一般的な事件での相場は、150万円から300万円程度となることが多いです。
例えば、窃盗や薬物事件(大麻など)では150万円~200万円、詐欺や強制わいせつなどの事件では200万円~300万円が一つの目安となります。
この金額は、被告人が「これを失うのは痛い」と感じ、逃亡を思いとどまらせるに足る額でなければならない、という考え方に基づいています。
重要なことなので繰り返しますが、この保証金は裁判が無事に終われば全額返還されます。
一方、弁護士費用は、保釈申請という専門的な弁護活動に対する対価であり、こちらは返還されるものではありません。
費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には着手金と成功報酬で構成されています。
具体的な金額については、ご依頼いただく際に弁護士から詳しくご説明いたします。
保釈申請時や保釈後の生活で気をつけるべきポイント
保釈は、単に身柄が解放されるだけではありません。
社会生活に戻るにあたり、守るべきルールや注意点があります。
これらを軽視すると、せっかく認められた保釈が取り消されてしまう可能性もあるため、十分な理解が必要です。
保釈申請時には弁護士への依頼が原則
法律上、保釈申請はご本人やご家族でも可能ですが、その手続きは非常に専門的です。
保釈を認めてもらうためには、法律の要件を満たしていることを的確に主張し、裁判官や検察官が抱くであろう懸念(逃亡や証拠隠滅のおそれ)を一つひとつ丁寧に取り除いていく必要があります。
弁護士は、過去の多くの経験から、どのような主張が効果的で、どのような資料を提出すれば裁判官を説得できるかを熟知しています。
裁判官との面接で直接交渉するなど、専門家でなければ難しい活動を通じて、保釈が許可される可能性を最大限に高めることができます。
大切なご家族の早期の身柄解放を望むのであれば、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが、最も確実な道と言えるでしょう。

保釈後は指定の条件を守って生活しなくてはならない
保釈が許可される際には、裁判所から必ずいくつかの条件(保釈条件)が付されます。
これは刑事訴訟法第93条に基づくものです。
代表的な条件には、以下のようなものがあります。
- 定められた住居に居住すること(住居の制限)
- 裁判所の許可なく、長期の旅行や海外渡航をしないこと
- 事件の関係者(被害者、証人、共犯者など)と一切接触しないこと
- 裁判所の呼び出しには必ず応じること
これらの条件に違反した場合、刑事訴訟法第96条に基づき、検察官の請求または裁判所の職権によって保釈が取り消され、再び身柄を拘束される可能性があります。
さらに、納付した保釈保証金の全部または一部が没収(没取)されてしまうこともあります。
例えば、事件が愛媛県迷惑行為防止条例に違反する行為(つきまとい等)に関するものであった場合、保釈条件として「被害者への一切の接触禁止」が定められることは確実です。
この場合、たとえ謝罪の気持ちからであっても、被害者に手紙を送ったり、電話をかけたり、住居の近くを訪れたりする行為は、重大な条件違反とみなされます。
その結果、即座に保釈が取り消され、高額な保証金を失うことになりかねません。
保釈後の生活は、決して完全に自由というわけではなく、常に裁判所から課された条件を遵守する必要があるのです。
保釈申請が却下されたときの対処法
万が一、保釈申請が裁判官に却下されてしまったとしても、それで全てが終わるわけではありません。
不服を申し立てるための手段が残されています。
却下決定に対しては、準抗告(じゅんこうこく)という手続きをとることができます。
これは、決定を下した裁判官とは別の3人の裁判官からなる合議体に対して、もう一度判断を求めるものです。
準抗告が認められれば、元の決定が覆り、保釈が許可されることがあります。
また、一度却下された後でも、状況に変化があれば再度保釈を申請することが可能です。
例えば、公判が進んで証人尋問が終了し、「証拠隠滅のおそれが低下した」と主張できるようになった段階で、改めて申請を行うことは有効な手段です。
諦めずに、弁護士と次の戦略を練ることが重要です。
保釈申請についてよくある質問
ここでは、保釈申請に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
保釈申請は何日かかる?
弁護士が裁判所に保釈請求書を提出してから、裁判官が判断を下すまで、通常2~3営業日が目安です。
土日祝日は裁判所の審査が進まないため、週末を挟むとさらに日数がかかります。
保釈申請が通る確率は?
法務省が公表している「令和5年版 犯罪白書」によると、令和4年(2022年)に地方裁判所で終結した事件のうち、勾留された被告人が保釈された割合(保釈率)は32.2%でした。
この数字だけを見ると高く感じられないかもしれませんが、重要なのはその推移です。
保釈率は平成15年(2003年)には12.7%でしたが、そこから一貫して上昇傾向にあります。
これは、裁判所の運用が、以前よりも保釈を認める方向に変化してきていることを示しており、決して諦めるべき状況ではないと言えます。
保釈申請が却下される主な理由は?
最も多い理由は、刑事訴訟法第89条4号に定められている「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」と裁判所に判断されるケースです。
特に、事件の事実を争っている(否認している)場合や、共犯者がいる場合、被害者や証人との間で示談が成立していない場合などに、この理由で却下される傾向があります。
まとめ
ご家族が逮捕・起訴され、身体拘束が続く状況は、ご本人にとっても、支えるご家族にとっても、計り知れないほどの不安とストレスを伴います。
保釈申請は、その長く暗いトンネルに差し込む一筋の光であり、社会復帰に向けた重要な第一歩です。
この記事で解説したように、保釈手続きには法律上の厳格な要件や流れがあり、専門的な知識と経験が不可欠です。
特に、裁判官を説得し、検察官の反対意見を乗り越えるためには、刑事事件に精通した弁護士の力が大きな助けとなります。
当事務所では、豊富な経験に基づき、保釈が認められやすいタイミングを慎重に見極め、個別の事案に応じた適切な内容で保釈請求を行うことで、保釈の可能性を最大限に高める弁護活動を行っています。
今、皆様がこの情報を調べていること自体が、大切なご家族を想う強い気持ちの表れです。
そのお気持ちを、具体的な行動へと繋げ、一日も早い身柄解放を実現するために、どうか一人で悩まず、専門家にご相談ください。

